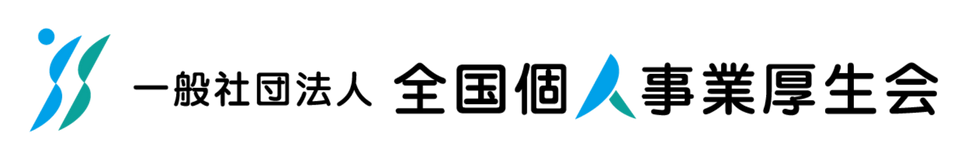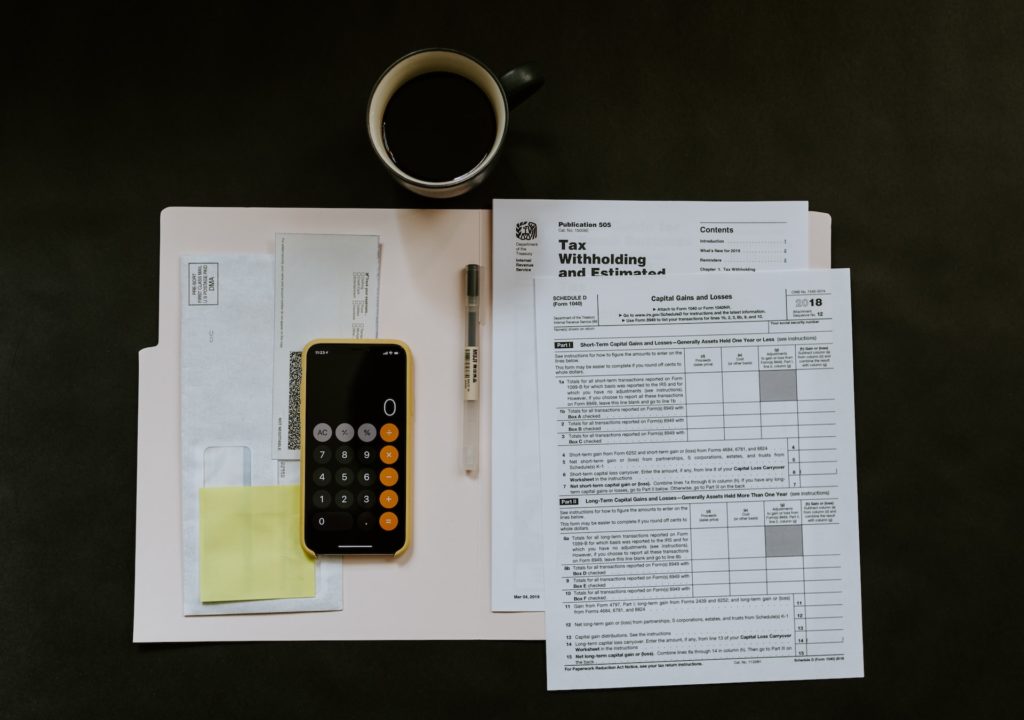消費税の確定申告方法についてご存じでしょうか?
課税事業者であれば消費税の納税額を正しく計算して確定申告する必要があります。
しかし個人事業主の多くは「え?消費税って確定申告する必要あるの?」と思うかもしれません。
そこで本記事では、個人事業主の消費税の確定申告方法について解説します。
消費税の確定申告の対象は?
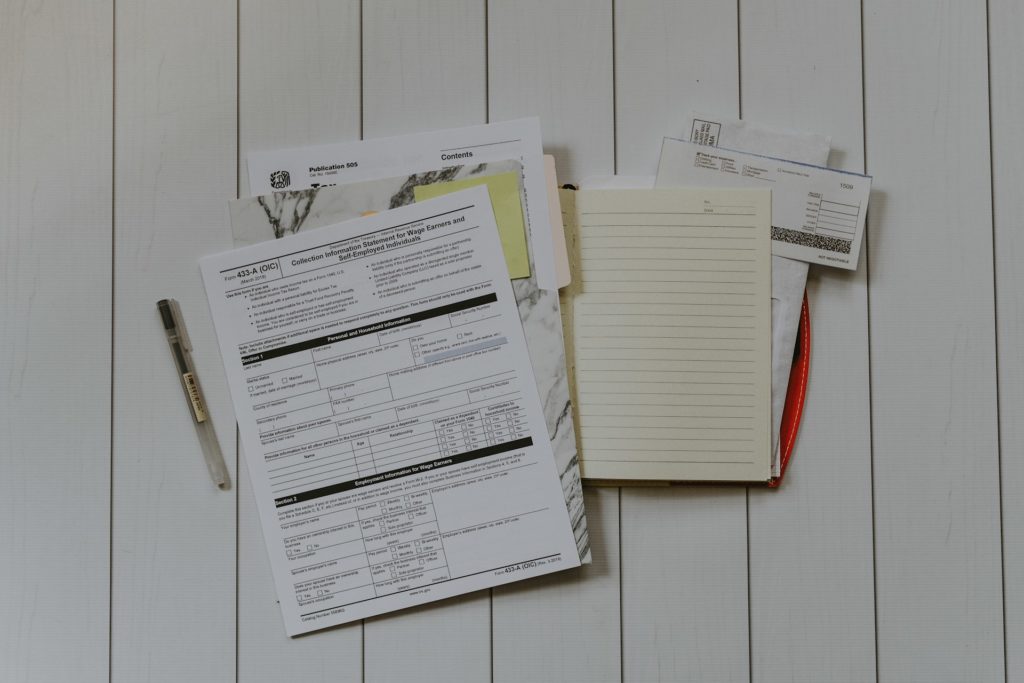
消費税は本来、消費者(商品やサービスの購入者)が納めるものであるため、個人事業主は関係ないように思うかもしれません。
しかし、個人事業主でも取引先から消費税を売上とあわせて預かる場合には納税する義務が生じます。
ただし消費税の納税は一定の条件において義務付けられるものです。
以下で必要なケースと不必要なケースについて解説するので、自身がどちらに当てはまるのか確認してみましょう。
個人事業主で消費税の納税が必要なケース
個人事業主で課税事業者である場合は、消費税の納税が必要です。
課税事業主となるのは、以下に該当する個人事業主です。
- 基準期間(1月1日~12月31日)における課税売上高が1,000万円を超える
- 適格請求書発行事業者に登録している
- 特定期間(前年の1月1日~6月30日)における課税売上高が1,000万円を超える
いずれかに該当しているのであれば消費税の納税をおこなわなければいけません。
個人事業主で消費税の納税が不必要なケース
個人事業主で免税事業者である場合は、消費税の納税義務は発生しません。
免税事業主となるのは、以下に該当する個人事業主です。
- 基準期間(2年前)における課税売上高が1,000万円以下
- 適格請求書発行事業者に登録していない
- 特定期間(前年の1月1日~6月30日)における課税売上高が1,000万円以下
上記に該当するのであれば、消費税の納税については一旦置いておいて問題ありません。
もし売上が900万近くまでになった場合には、事前に知っておいた方が良いでしょう。
基準期間と特定期間について
個人事業主で課税事業者になるかどうかは、期間によって異なります。
基準期間と特定期間と分かれているので、いまいちいつから課税されるのかわからない人もいるでしょう。
そこで、期間についてもう少し詳しく解説します。
まず、基準期間と特定期間には以下の違いがあります。
- 基準期間…2年前の1月1日~12月31日
- 特定期間…1年前の1月1日~6月30日
いずれにおいても課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となります。
この関係性をわかりやすく示すと、以下のようになります。
| 令和4年の課税売上高(基準期間) | 令和5年(特定期間) | 令和6年 |
| 1,000万円超 | – | 課税事業者となる |
| 1,000万円以下 | 1,000万円超 | 課税事業者となる |
| 1,000万円以下 | 1,000万円以下 | 免税事業者 |
上記のように課税事業者か免税事業者かを判断するには、2年前と1年前の課税売上高を確認する必要があります。
消費税の計算方法
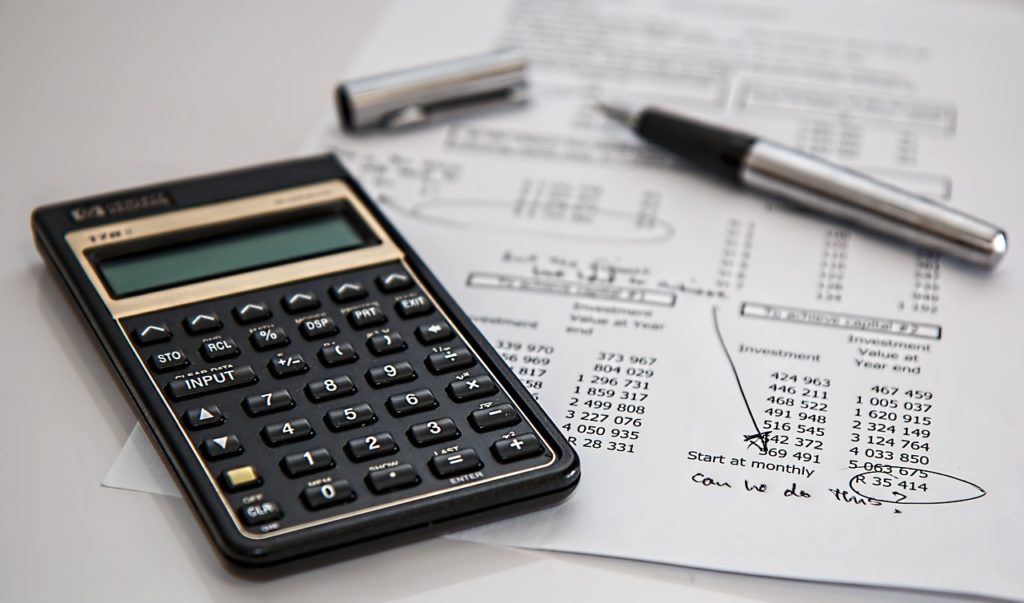
消費税の計算方法には、以下の3種類があります。
- 原則課税方式
- 簡易課税方式
- 2割特例
個人事業主の売上高や適格請求書発行事業者への登録状況によってどの方法を用いるかは異なります。
とくに2023年10月1日から課税事業者になった個人事業主は2割特例が適用できるようになったので、状況に応じて適した計算式を選択するようにしましょう。
以下でそれぞれの方法について解説します。
原則課税方式
原則課税方式は、1年間に預かった消費税から事業主が実際に支払った消費税を差し引く方法です。
原則課税方式のほか、一般課税方式・本則課税方式と呼ばれます。
計算例は以下のとおりです。
【課税売上高の消費税-経費にかかった消費税=消費税額】
なお、消費税の計算をする際には10%の取引と8%の取引に区分する必要があるので注意しましょう。
簡易課税方式
簡易課税方式は、基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者のみが選択できる方法です。
適用を受ける必要があるので、課税期間がはじまる日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出しなければいけません。
計算例は以下のとおりです。
【課税売上高の消費税額-(課税売上高の消費税額×みなし仕入率)=消費税額】
みなし仕入れ率は業種ごとに定められていますので、以下を参考にしてください。
| 業種 | みなし仕入れ率 |
|---|---|
| 第1種事業(卸売業) | 90% |
| 第2種事業(小売業・農業・林業・漁業) | 80% |
| 第3種事業(農業・林業・漁業・鉱業・建設業・製造業・電気業等) | 70% |
| 第4種事業(飲食店業等) | 60% |
| 第5種事業(運輸通信業・金融業・保険業・サービス業) | 50% |
| 第6種事業(不動産業) | 40% |
2割特例
2割特例は、2023年10月1日からはじめて課税事業者となった場合(基準期間・特定期間ともに1,000万円以下)に適用される軽減措置です。
条件さえ満たしていれば手続きの必要なく適用されます。
しかし確定申告の際に2割特例を適用した旨を記載しなければなりません。
2割特例の計算例は、以下のとおりです。
【売上にかかる消費税額-(売上にかかる消費税額×80%)=消費税額】
他の方式よりも納税負担を抑えられますので、インボイス対応のために課税事業者となった個人事業主は2割特例を利用しましょう。
【個人事業主向け記入例】消費税の確定申告の書き方

消費税の確定申告の書き方について解説します。
とくに消費税申告書の書き方を入念に解説しますので、初めて申告をおこなう個人事業主は参考にしてください。
基本的なステップは以下のとおりです。
- 消費税申告書を用意する
- 申告に必要な添付書類を用意する
- 申告期限内に手続き
以下で一つずつ確認しながら進めていきましょう。
1.消費税申告書を用意する
まずは消費税申告書を用意しましょう。
申告書は課税方式によって異なるので、適切なものを選んでください。
消費税申告書は以下の方法で手に入れられます。
- 国税庁サイトでダウンロード
- 確定申告書等作成コーナー
- 税務署窓口
「国税庁サイト」「確定申告書等作成コーナー」であればインターネット環境があれば用意できるのでおすすめです。
消費税申告書の記入方法については以下で解説していきます。
課税標準額
【売上金額×100/108=課税標準額】
課税標準額が税率を掛ける前の金額です。
税額計算の「もと」となる金額を意味しているので、計算の便宜上、千円未満は切り捨ててください。
消費税額
【課税標準額×6.3/100=消費税額】
課税標準額に消費税率をかけて、売上金額に含まれる消費税額を計算します。
控除対象仕入税額
【仕入れ金額+経費合計-課税仕入れ=A】
【A×6.3/108=控除仕入れ税税額】
仕入れ金額に含まれる消費税を計算します。
経費に含まれる消費税も控除の対象となるので、仕入れ金額と経費の合計を足してください。
控除税額小計
【控除対象仕入れ税額+返還等対価に係る税額+貸し倒れに係る税額=控除税額小計】
差引税額・納付税額・差引税額
【消費税額-控除税額小計=差引税額・納付税額・差引税額】
課税資産の譲渡等の対価の額・資産の譲渡等の対価の額
ここでは「課税標準額」を記載します。
納税額・納付譲渡割額
【納付税額×1.7/6.3=納税額・納付譲渡割額】
納付税額は国税6.3分の消費税額なので、×1.7/6.3をすることで1.7%分の地方税分を求められます。
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額
【納付税額+納付譲渡割額=消費税及び地方消費税の合計税額】
2.申告に必要な添付書類を用意する
消費税申告書の記入ができたら、そのほかの書類を用意しましょう。
必要書類は課税方式ごとに異なります。
| 課税方式 | 添付書類 |
|---|---|
| 原則課税方式 | ・付表1-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表 ・付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 |
| 簡易課税方式 | ・付表4-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表 ・付表5-3 控除対象仕入税額等の計算表 |
| 2割特例 | ・付表6 税率別消費税額計算表 |
上記を参考にして、課税方式に合った書類を用意するように注意しましょう。
3.申告期限内に手続き
各種書類が用意できたら申告期限内に手続きを終えてください。
個人事業主の場合は翌年3月31日までと定められていますので、期限を過ぎないように注意しましょう。
まとめ

確定申告を正しくできるように、今回紹介した消費税申告もおこなってみてください。
今後、個人事業主として仕事をしていく上で毎年訪れるものなので早い段階で理解しておきましょう。
また、確定申告を正しくおこなうことで具体的にどれだけの金額が手元に残ってどれだけの金額が出ていったかを把握できます。
事業主として利益・経費を把握するためにも確定申告は大切ですから、ぜひ面倒くさがらずにおこなってください。
そして、もし確定申告をして「手元に残る金額はこれだけか……」と感じたら、社会保険料の見直しを考えてみましょう。
基本的に個人事業主は国民健康保険や国民年金に加入しますが、個人事業主でも社会保険に加入して、月々の保険料を安くできるケースがあるのです。
以下のページでどのようにお得になるのかを解説していますので、ぜひ参考にしてください。