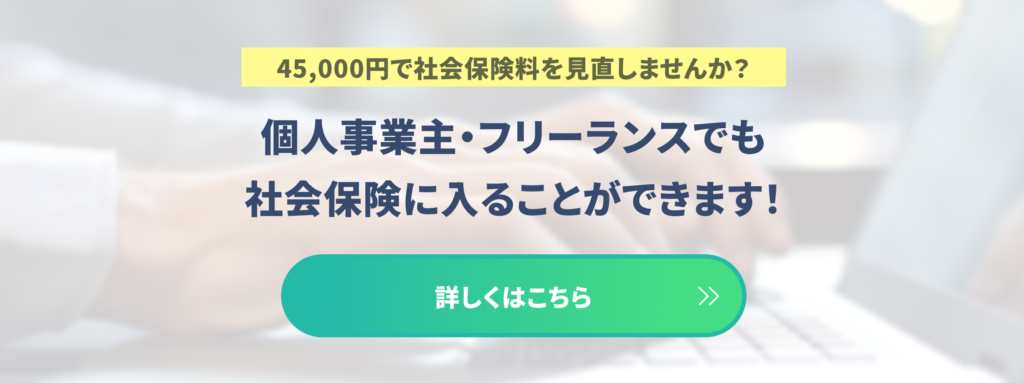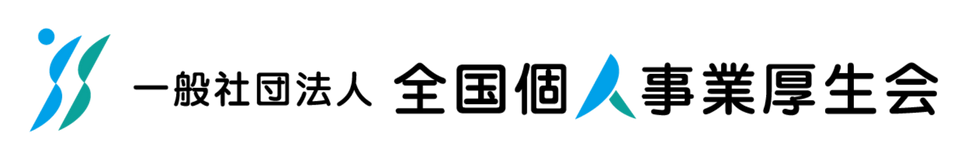令和6年から始まる定額減税は、物価上昇によって生活が苦しくなっている国民の負担軽減を目的に行われる減税措置です。
会社員は自分で手続きをしなくても恩恵を受けられますが、個人事業主は収入や家族構成に応じて対応が異なります。
そこで今回は、定額減税を受けるための方法について解説します。
定額減税の仕組みが分からない個人事業主は、本記事を参考にしてください。
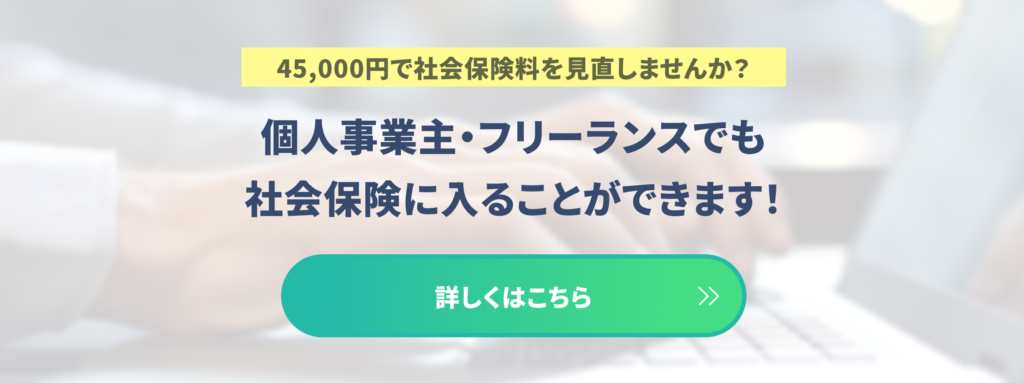
令和6年から始まる定額減税とは?
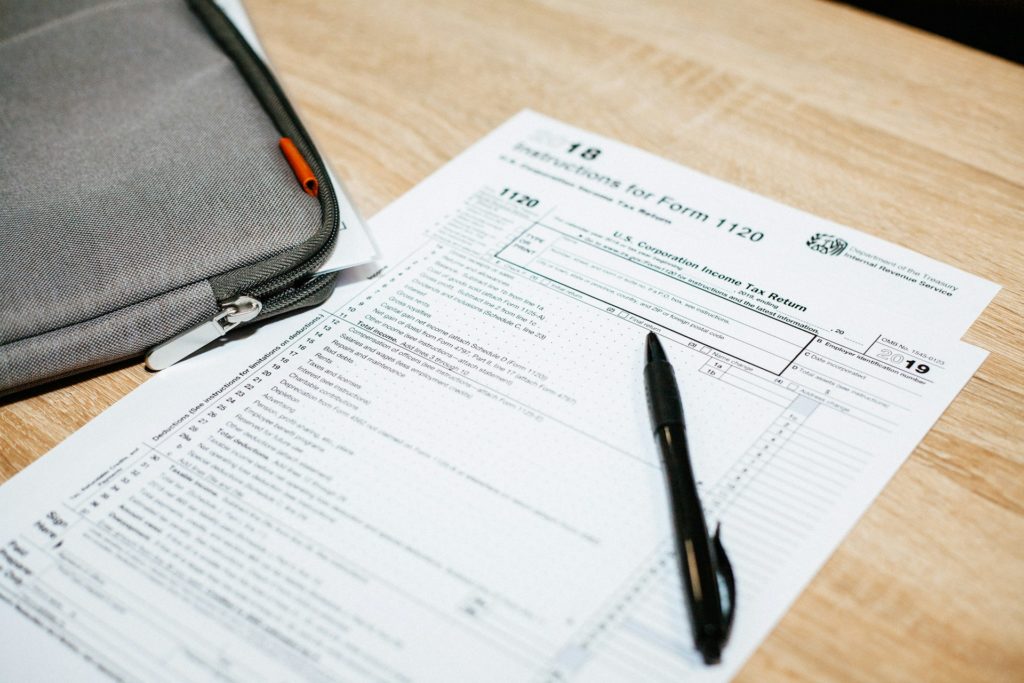
定額減税は、令和6年6月からはじまる減税措置です。
令和5年11月2日の閣議で、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」が決定されました。
この閣議決定に至った背景について解説していきます。
定額減税を導入する背景
定額減税は、物価上昇にともなう国民負担を軽減するために導入されました。
前述の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、賃上げが物価上昇に追いついていない国民のために、期間限定の減税措置が定められました。
現在の日本で起きている物価上昇には、円安も大きく関わっています。
日本は資源が乏しく、かつてから食糧やエネルギー資源など、様々なものを輸入に頼ってきました。
しかし、円安によって輸入コストが上昇し、穴埋めするために上昇したコストを価格に転換せざるを得ないのが現状です。
このまま物価上昇を維持してデフレ脱却を目指したい政府は、一時的な減税措置を講じて国民負担の緩和に踏み切りました。
定額減税の対象者
定額減税の対象者は、以下に該当する方です。
・令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)。
・給与収入のみの方で子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下。
業種や働き方を問わず、多くの国民が定額減税の対象者になることが分かります。
当然、一般労働者だけではなく、年金受給者や事業所得者も対象になります。
定額減税はどのくらい減税になるか
定額減税で減額される金額は1人あたり所得税が3万円、住民税が1万円です。
扶養家族が3人いる家族の場合、所得税と住民税の減税額は以下のようになります。
- 所得税:3万円×4人=12万円
- 住民税:1万円×4人=4万円
合計すると、年間の減税額は16万円です。
この定額減税のみで食費や光熱費の増額分を賄うのは難しいですが、少しでも手取り額が増えるのは国民にとって朗報です。
定額減税では扶養家族の範囲に注意が必要

税法上の扶養家族と、今回の定額減税に含まれる扶養家族は異なります。
定額減税の対象になる扶養家族の範囲について解説します。
扶養家族の対象年齢
税法上では、16歳未満の子は所得税の扶養控除を受けられません。
しかし、定額減税では16歳未満の子も扶養家族の対象になります。
令和6年度中に誕生した子どもは所得税の定額減税の対象となるので、出産した家族や今年中に出産を予定している家族は申告を忘れないようにしましょう。
令和6年度中に誕生した子どもは住民税の定額減税は受けられない
令和6年度中に誕生した子どもは、住民税の定額減税だけは受けられません。
所得税の計算は令和6年1月1日~令和6年12月31日までの所得をもとに控除額が計算されますが、住民税は前年度の所得をもとに控除額を計算するためです。
令和6年度中に誕生した子どもは前年度の記録がないため、住民税の定額減税は受けられない仕組みになっています。
個人事業主が所得税の定額減税を受ける2つの方法
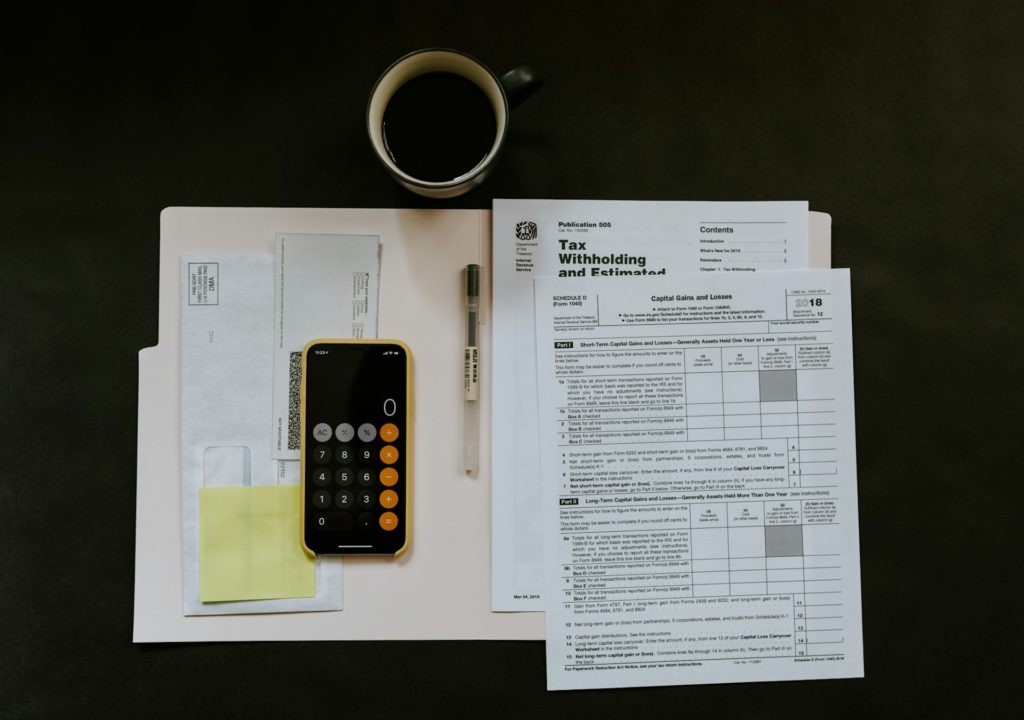
個人事業主が定額減税を受けるためには、以下の2つの方法があります。
- 令和6年度の確定申告で定額減税を受ける
- 令和6年1期の予定納税で定額減税を受ける
国税庁によると、予定納税は前年分の所得金額や税額などをもとに計算した予定納税基準額が15万円以上となる個人事業主が対象になります。
それぞれの申請方法について、詳しく解説します。
令和6年度の確定申告で定額減税を受ける
個人事業主は毎年確定申告を行っていますが、令和6年度の確定申告を行う際に定額減税のうち所得税分の控除を受けられます。
そのため、減税が反映されるのは確定申告が始まる令和7年2月以降となります。
給与所得者は令和6年6月から定額減税の控除を受けられるので、控除のタイミングが異なることを覚えておきましょう。
令和6年1期の予定納税で定額減税を受ける
予定納税する個人事業主は、確定申告前に定額減税の控除を受けられます。
令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額から定額減税の控除を受けられるので、令和6年7月に本人分は自動で控除されます。
1期分で控除しくれなかった場合は2期分から控除され、2期分でも控除しきれない場合は確定申告後に還付されるので心配ありません。
個人事業主が住民税の定額減税を受ける方法

住民税の定額控除は令和6年度1期分から直接控除されるため、特別な手続きをする必要はありません。
居住する自治体から送付される「住民税決定通知書」に定額減税の額が記載されるので、書類が届いたら確認しましょう。
住民税も所得税の予定納税と同様に、1期分で控除しきれない場合は2期分から控除されるようになっています。
扶養家族の住民税で定額減税を受ける方法
扶養家族がいる個人事業主は、その扶養家族分の定額減税も受けられます。
こちらも確定申告と予定納税で方法が異なるため、それぞれ解説します。
確定申告で定額減税を受ける
確定申告で扶養家族分の定額減税を受けるためには、令和6年度の確定申告書に扶養家族を記載して提出します。
確定申告書が受理されると、扶養家族分の減税を受けられます。
対象となる扶養家族の定義は、以下のとおりです。
- 令和6年12月31日現在で納税者本人と生計を1つにしていて、合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の配偶者や親族
該当する扶養家族がいる個人事業主は、確定申告書に扶養家族の人数を記載して定額減税を受けましょう。
予定納税で定額減税を受ける
予定納税で扶養家族分の定額減税を受けるためには、「予定納税額の減額申請書」を令和6年7月31日までに提出しなくてはいけません。
予定納税の減額申請を行う際の手順を解説します。
- 国税庁のホームページから「予定納税額の減額申請書」をダウンロード
- ダウンロードした減額申請書に必要事項を記載
- 減額申請書と添付書類を管轄の税務署へ提出
減額申請書が受理されると第1期分予定納税額から控除が始まり、控除しきれない金額は第2期分予定納税額から控除されます。
確定申告と異なり別途手続きが必要になりますが、予定納税する個人事業主は忘れずに減税申請書を税務署へ提出しましょう。
従業員を雇用している場合
従業員を雇用している個人事業主は、従業員分の定額減税を行う必要があります。
令和6年6月以降、毎月の給与から3万円になるまで所得税の控除を行い、給与明細に記載しなくてはいけません。
毎月の所得税が5,000円だった場合、以下のような処理が必要です。
- 令和6年6月所得税:5,000円→0円
- 令和6年7月所得税:5,000円→0円
- 令和6年8月所得税:5,000円→0円
- 令和6年9月所得税:5,000円→0円
- 令和6年10月所得税:5,000円→0円
- 令和6年11月所得税:5,000円→0円
上記のように、毎月所得税の控除を行うことが義務付けられています。
住民税については、事業主が個別に計算や処理を行う必要はありません。
自治体が必要な計算を行い、通知された住民税をこれまでと同じように天引きできます。
定額減税について疑問のある個人事業主はどうする?

定額減税について疑問がある個人事業主は、以下の機関で質問できます。
- 国税庁のチャットボット(ふたば)
- 最寄りの税務署
国税庁のホームページにアクセスすると、AIチャットボットが24時間いつでも質問に回答してくれます。
もし、国税庁のAIチャットボットで解決しない場合は、最寄りの税務署に問い合わせも可能です。
急に始まった減税措置なので、内容がよく分からないと感じている方も多いでしょう。
そんな時はうやむやにせずに、上記に問い合わせして控除を正しく受けられるようにしてください。
定額減税は個人事業主だけではなく扶養家族も対象になる

定額減税は、働いている個人事業主だけではなく、扶養家族の人数分控除を受けられる減税措置です。
確定申告を行うか予定納税を行うかで、控除を受ける方法やタイミングは異なります。
しかし、定額減税で受けられる控除額は1人あたり4万円で、1年間限定です。
物価上昇で少しでも出費を抑えたい個人事業主には、国民健康保険を社会保険に切り替えて、毎月の保険料を抑える方法が効果的です。
特に、扶養家族のいる個人事業主は家族の人数分国民健康保険料が増えるので、社会保険に切り替えるメリットが大きくなります。
毎月の保険料がどのくらい安くなるか無料相談できるので、以下のリンクから詳細をご確認ください。