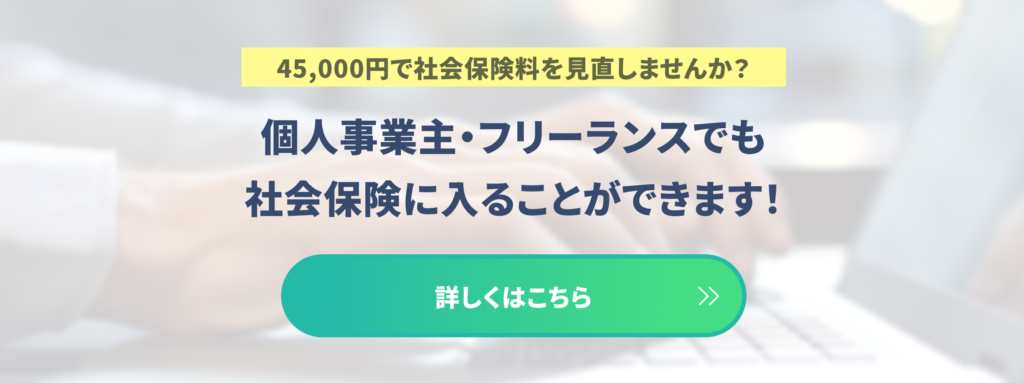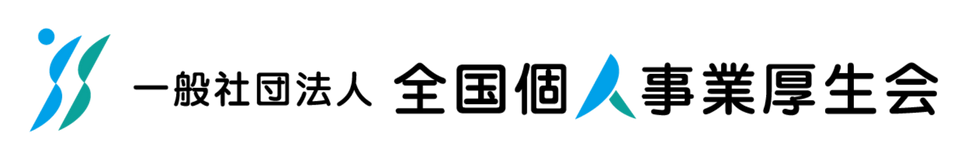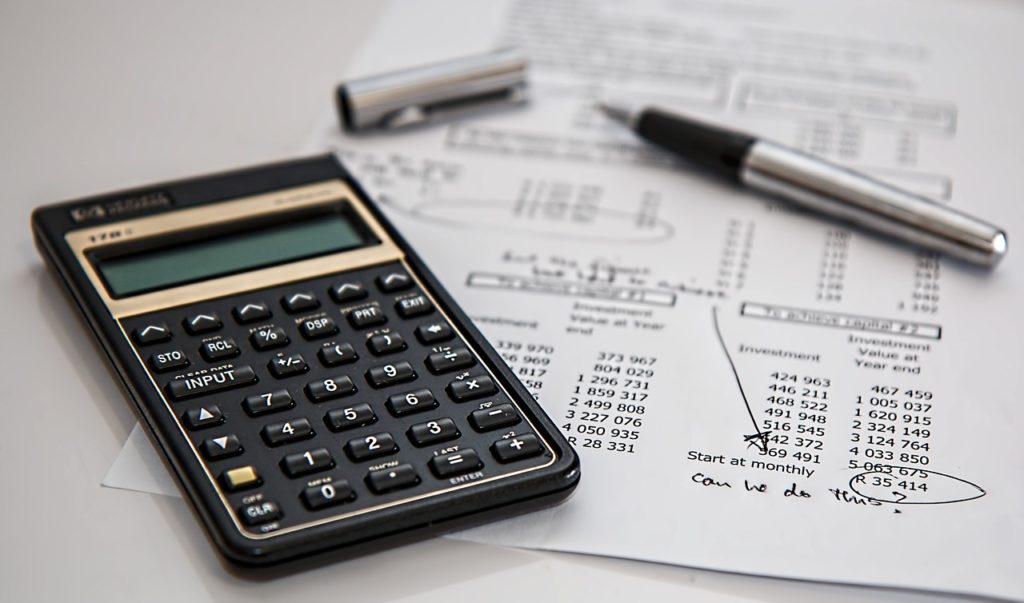会社員を辞めて個人事業主として独立する人は増加していますが、個人事業主は社会保険や年金の仕組みが大きく変わるため不安を感じることも珍しくありません。
これまでは毎月の給与から天引きされていたため社会保険や年金に関心がなかった人も、個人事業主になって自分で納付するようになってその金額に驚くケースがあります。
独立する際に、社会保険の任意継続と国民健康保険のどちらに加入したらいいか迷ってしまう人もいるでしょう。
今回は、社会保険の任意継続と国民健康保険、それぞれのメリットデメリットと独自に社会保険に加入する方法について解説していきます。
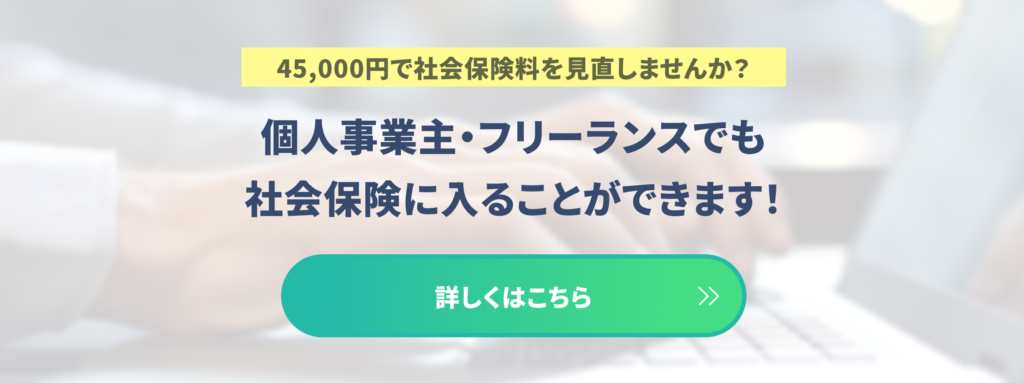
個人事業主になってすぐに社会保険料が高くてびっくりするケースがある

個人事業主になると、社会保険料の負担が急に大きくなることがあります。
会社員時代は会社と折半で社会保険料を支払っていましたが、個人事業主になると事業主負担分も含めて全額自己負担になるためです。
東京都の自己負担の例で解説すると、令和6年3月からの健康保険料は介護保険に該当しない場合で9.98%、介護保険に該当する場合は11.58%です。
会社員の標準報酬月額が30万円だった場合、介護保険に該当しない場合の自己負担は月額14,970円、介護保険に該当する場合の自己負担は月額17,370円になります。
東京都大田区にある国民健康保険料試算入力フォームを使って同じく月額の収入が30万円だった場合、月額35,819円でした。
会社員時代と同じ月収でも、個人事業主の社会保険料は約20,000円跳ね上がることになります。
何も知らずに独立してしまうと、国民健康保険料の金額に驚くのは無理もありません。
個人事業主の立場になって初めて、会社員時代には見えていなかった社会保険料の存在の大きさに気づかされます。
個人事業主になる際は、社会保険料の負担増加を見込んで独立準備しておくことが大切です。
退職から2年間は勤務先の社会保険を任意継続できる

会社を退職して個人事業主になった場合でも、退職から2年間は勤務先の健康保険と厚生年金を任意で継続できます。
これは任意継続制度と呼ばれ、退職後も一定期間、会社員時代と同じ条件で社会保険に加入できる仕組みです。
任意継続の保険料は、前職の標準報酬月額に基づいて計算されます。
会社員時代は会社と折半で負担していた保険料ですが、個人事業主になってからは全額自己負担することになります。
それでも国民健康保険と比較すると安くなるケースが多いので任意継続を利用する個人事業主は少なくありません。
会社員時代から引き続き手厚い社会保障を受けられるのが、任意継続制度の特徴です。
ただし、任意継続には加入期限があることを忘れてはいけません。
任意継続を開始してから2年経過すると資格を喪失し、強制的に国民健康保険に切り替わることになります。
また、任意継続の保険料は前職の標準報酬月額で決まるため、前職の収入が高かった場合は保険料負担も大きくなります。
自分の収入状況を踏まえて、任意継続の加入を吟味することが大切です。
個人事業主が任意継続に加入するメリットデメリット

国民健康保険が高いなら任意継続を利用したいと考える個人事業主も多いと思いますが、任意継続にはメリットデメリットがあります。
それぞれの特徴をよく理解してから、任意継続に加入するかどうかを判断しましょう。
任意継続のメリット
個人事業主が任意継続制度を利用するメリットは、何よりも社会保険料が軽減されることです。
全額自己負担とはいえ、国民健康保険よりも割安な保険料で会社員時代と同じく厚生年金にも加入できるのが最大のメリットです。
また、健康保険の給付を継続して受けられる点も忘れてはいけません。
病気やケガで大きな手術が必要になった場合、自己負担の上限設定があるのも任意継続のメリットです。
任意継続は、個人事業主になったばかりの時期の社会保障を手厚く支えてくれる制度だといえます。
事業の立ち上げ期は収入が不安定になりがちですが、任意継続なら会社員時代とほぼ同じ保障内容で加入できるため、安心して事業に注力できます。
任意継続のデメリット
任意継続にはいくつかのデメリットもあります。
まず、加入期間が最長2年間と決められている点です。
2年を過ぎると任意継続の資格を失い、強制的に国民健康保険に切り替わります。
また、保険料が前職の標準報酬月額に基づいて計算されるため、前職の収入が高かった人にとっては社会保険料が高くなる可能性があります。
個人事業主としての収入が少なくなっても、高額な社会保険料を支払い続けなければならないのはデメリットです。
さらに、任意継続は傷病手当金や出産一時金の支給対象から除外されます。
任意継続したから補償がもらえると考えていると、予定外の出費となってしまうので注意しましょう。
加えて、任意継続は健康保険と厚生年金がセットになっています。
厚生年金は将来の年金受給に直結するため加入しておくことが望ましいのですが、前職の標準報酬月額によっては国民年金よりも負担が大きくなります。
個人事業主が国民健康保険に加入するメリットデメリット

個人事業主は基本的に国民健康保険に加入することになりますが、その国民健康保険にもメリットデメリットがあります。
他の保険があるなら切り替えたいと感じるかもしれないので、国民健康保険のメリットデメリットも解説します。
国民健康保険のメリット
個人事業主が国民健康保険に加入するメリットは、何よりも保険料が収入に応じて決まる点です。
事業の収入が少ないうちは保険料も低く抑えられるため、負担感が少なくて済みます。
また、国民健康保険は職業や年齢に関係なく、住んでいる自治体の住民であれば誰でも加入できる手軽さも魅力です。
個人事業主になって社会保険をどうするか迷ったときでも、とりあえず国民健康保険に加入しておけば無保険状態を避けられます。
国民健康保険は事業の成長に合わせて保険料が上下するため、収入の変動に柔軟に対応できる点もメリットです。
個人事業主の収入は変動しやすいものですが、国民健康保険なら無理なく保険料を納められるでしょう。
国民健康保険のデメリット
国民健康保険の最大のデメリットは、保険料が高額になりやすい点です。
特に個人事業主として高収入を得ている場合、予想以上に保険料負担が大きくなることがあります。
また、傷病手当金がないなど、保障面でのデメリットもあります。
個人事業主は病気やケガで長期間働けなくなると収入が途絶えるリスクがありますが、その際の所得保障は国民健康保険では受けられません。
自治体によって国民健康保険の内容に差があるため、住んでいる地域によっては不利になることもあるでしょう。
国民健康保険は手軽に加入できる反面、社会保険料や保障内容の面で不利になることも多いのです。
個人事業主の状況に応じて、メリットとデメリットを見極める必要があります。
個人事業主が社会保険を任意継続するかは前職の収入による

個人事業主が社会保険を任意継続するかどうかを判断する際は、前職の標準報酬月額が大きなポイントになります。
任意継続の保険料は前職の標準報酬月額に基づいて計算されるため、前職の収入が高いほど保険料負担も大きくなるためです。
例えば、前職の標準報酬月額が50万円だった場合の健康保険は、介護保険に該当しない場合で49,000円、介護保険に該当する場合は57,900円になります。
さらに、厚生年金を全額自己負担すると91,500円になるため、月額の社会保険料は約150,000円になります。
令和6年度の国民年金は前職の標準報酬に関わらず月額16,980円なので、個人事業主としての収入が少ないうちは、任意継続は大きな重荷になるでしょう。
逆に、前職の収入が低かった場合は、任意継続のメリットが大きくなります。
保険料負担を低く抑えつつ、手厚い社会保障を受けられるので任意継続に加入した方が不安定な個人事業主の立ち上げ期を支えてくれます。
また、任意継続の保険料は2年間固定されるため、個人事業主としての収入が大きく伸びても保険料は上がりません。
事業が軌道に乗りつつあるときに、保険料の上昇を気にせずに済むのもメリットです。
個人事業主にとって、社会保険を任意継続するかどうかの判断は前職の標準報酬月額によって大きく左右されます。
自分の状況を見極め、任意継続と国民健康保険のメリットデメリットを比較検討して、後悔のない選択をすることが大切です。
個人事業主でも新しく社会保険に加入できる方法

社会保険に加入したいけれど全額自己負担になる任意継続は負担が大きいと感じる場合、新しく社会保険に加入することで会社員時代と同じくらいの自己負担で手厚い保障を受けられます。
全国個人事業厚生会では、個人事業主やフリーランスの方でも社会保険に加入できるサービスを用意しています。
社会保険の任意継続や国民健康保険に加入するよりも保険料を削減できる可能性があり、社会保険と厚生年金に加入することとなるので手厚い補助をうけることもできます。
特に扶養家族のいる個人事業主は年間で100万円以上の社会保険料を節約できたケースもあるので、保険料が高いと感じてる人は気軽に問い合わせしてみてください。
大切な事業資金を最大限に活用するためには、いかに社会保険料を節約できるかが重要です。