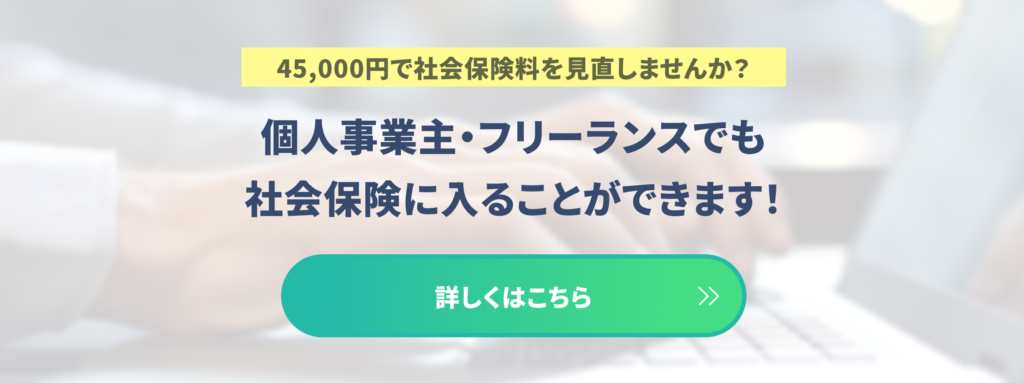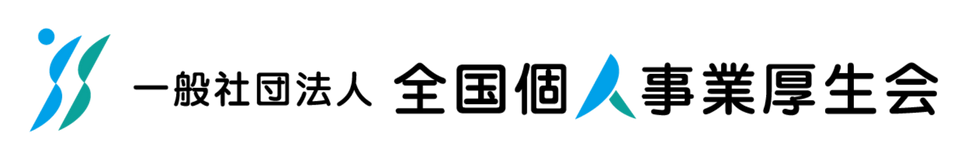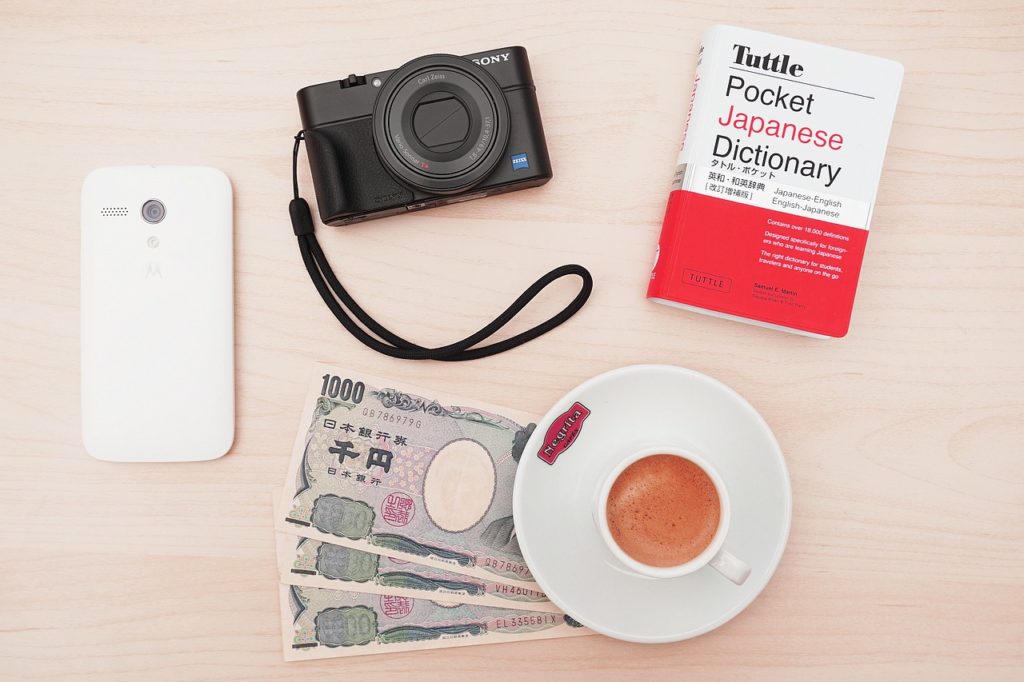個人事業主になると、会社員時代とは支払う税金が変わります。
個人事業主は税金の納付を自分で行うため、納める度に高いと感じている人もいるでしょう。
個人事業主が少しでも税金を抑えるためには、自分で節税対策をする必要があります。
本記事では、個人事業主が支払う税金の種類とおすすめの節税対策7選を紹介します。
さらに月々の支払いを抑えたい人には社会保険料の見直しも紹介しているので、参考にしてみてください。
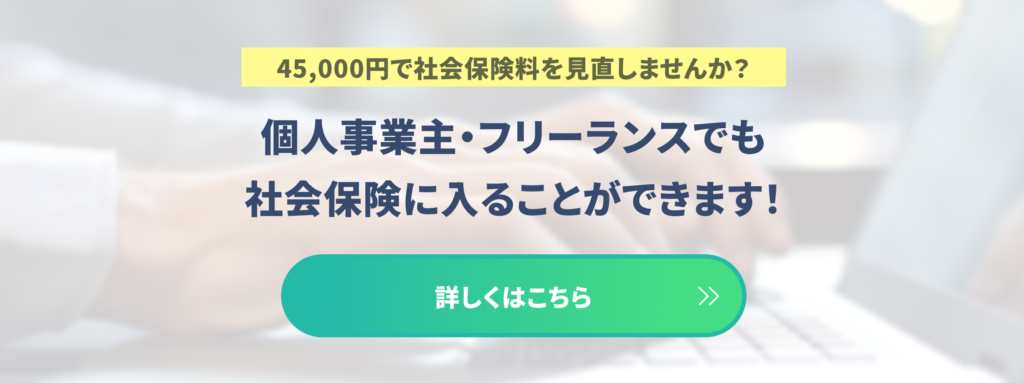
個人事業主が納める税金の種類

個人事業主は、以下のような税金を納付する義務があります。
- 住民税
- 所得税
- 消費税
- 個人事業税
特に、個人事業税は会社員時代に不要だった税金なので初耳の人もいるかもしれません。
収支の計画を立てる際に役立つので、それぞれの税金の税率や支払い回数について解説していきます。
住民税
住民税は、個人事業主が住んでいる都道府県や市区町村に納める税金です。
住民税では均等割と所得割の合計額を毎年支払います。
均等割は、住んでいる地域によって納付する住民税の金額が変わるのが特徴です。
所得割は前年度の所得を基に以下の計算式で求められます。
(前年の所得―所得控除)×(都道府県民税が4%市区町村民税が6%)–税額控除
住民税も個人事業主の事業所得だけでなく、不動産所得や配当所得なども含めた総所得金額を基に計算されます。
住民税は毎年6月に税額が決まり、原則として6月(第1期)、8月(第2期)、10月(第3期)、翌年1月(第4期)のそれぞれ末日までが期日になっています。
それぞれの支払いが難しい場合は、自治体に連絡して毎月納付に変更することも可能です。
所得税
所得税は、個人事業主が国に納める税金です。
所得税は前年の総所得から控除を差し引いた金額に応じて計算されます。
所得金額に応じて税率が変わる超過累進課税方式が採用されており、それぞれの所得に応じた税率と控除額は以下の通りになっています。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
例えば、控除を差し引いて課税される所得金額が200万円だった場合、税率10%をかけた金額から控除額の97,500円を差し引いた102,500円が納付する所得税です。
所得税を現金で支払う際の期日は確定申告の期限と同日の3月15日、振替口座で納税する場合は4月下旬に指定口座から引き落としされます。
所得税は、個人事業主の事業所得だけでなく、不動産所得や配当所得なども含めた総所得金額を基に計算されます。
消費税
消費税は、商品やサービスを購入する際に発生する税金です。
商品やサービスを提供して請求した消費税は、所得に含まれず国に納めなくてはいけません。
以前は2年前までの売上が1,000万円以下の事業者や、開業して2年未満の事業者は消費税の免税対象者でした。
しかし、2023年10月からインボイス制度が始まり、売上が1,000万円以下の場合も消費税の納税義務が発生するようになっています。
消費税は、以下の計算方式で求められます。
課税売上にかかる消費税額 – (課税売上にかかる消費税額 × みなし仕入れ率)
みなし仕入れ税率は業種によって異なるので、以下の表にまとめました。
| 事業区分 | みなし仕入れ税率 | 該当する事業 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業) |
| 第2種事業 | 80% | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) |
| 第3種事業 | 70% | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業など |
| 第4種事業 | 60% | 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業など |
| 第5種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除く) |
| 第6種事業 | 40% | 不動産業 |
個人事業税
個人事業税は、個人で事業を営む人に課される地方税の1つです。
個人事業税の納税義務者は、事業から生じる所得が290万円を超える個人事業主です。
課税対象となる事業は、物品販売業、不動産貸付業、製造業など幅広い業種が該当します。
一方で、以下の業種は個人事業税の対象外となっています。
- 画家や漫画家など絵に関する業種
- 作詞・作曲など音楽に関係する業種
- 通訳や翻訳など言語に関する業種
- 運動関係の業種
- 農業や林業などの業種
- IT関係の業種
個人事業税は確定申告を行うと納付書が届き、8月と11月の年2回に分けて納付することになります。
個人事業主におすすめの税金対策7選

少しでも税金を安く抑えるためには、個人事業主自ら税金対策をしなくてはいけません。
個人事業主におすすめの税金対策は、以下の7選です。
- 家事按分を使う
- 短期前払費用の特例を活用する
- 経営セーフティ共済を使う
- 小規模企業共済に加入する
- 所得控除を受ける
- 青色申告をする
- 30万円未満の固定資産を一括経費にする
上記の解説をしていくので、自分にできる税金対策があれば積極的に取り入れてみましょう。
家事按分を使う
家事按分とは、自宅の一部を事業用として使用している場合に、その使用部分に係る水道光熱費や家賃などを事業経費として計上する方法です。
家賃が10万円で自宅面積の20%を事業で使用している場合、毎月2万円を経費として計上可能です。
家事按分を適用するためには、自宅の間取り図や写真などを用意し、事業用として使用している部分を明確に線引きしておきます。
家事按分は面積だけでなく稼働時間などでも計算可能なので、税務調査が入った際に明確に説明できるように準備をしておきましょう。
また、仕事で自家用車を使用している場合はガソリン代、駐車場代、減価償却費や保険代も家事按分できます。
事業用として使用している部分が明確に区分されていない場合や按分割合が適切でない場合には、税務調査で指摘される可能性があるので注意しましょう。
適切な家事按分を行うことで、事業経費を適正に計上することができます。
自宅の一部や自家用車を事業に活用している個人事業主は、ぜひ家事按分の適用を検討してみましょう。
短期前払費用の特例を活用する
短期前払費用とは、事業に関連する費用のうち、支払った年度内に役務の提供を受けるものを指します。
例えば、事務所の家賃や保険料、前払いのリース料などが該当します。
通常、前払いした費用は支払った年度の必要経費として計上しますが、短期前払費用の特例を適用することで支払った年度の必要経費として一括計上することが可能です。
以下、短期前払費用の特例の適用要件をまとめました。
- 支払い日から1年以内に役務の提供を受けること
- 費用を事業年度末までに支払っていること
- 継続して役務の提供を受けること
- 継続して同じように経理処理をすること
短期前払費用の特例を適用することで、個人事業主は支払った年度の所得金額を抑えることができ、その分税負担を軽減することが可能です。
例えば、12月に翌年分の事務所の家賃を前払いした場合、通常はその年の必要経費にはなりませんが、特例を適用することでその年の必要経費として計上できます。
特例の適用要件を満たす前払費用がある場合は、積極的に活用を検討してみましょう。
経営セーフティ共済に加入する
個人事業主が加入できる経営セーフティ共済は、取引先が倒産したときに無担保・無保証人で掛金の最大10倍の借り入れができる制度です。
掛金は上限800万円まで積み立て可能で、掛金は全額を必要経費として計上できるため、個人事業主にとって有効な税金対策の1つです。
経営セーフティ共済は、月額5,000円から20万円の範囲内で自由に掛金を設定できます。
掛金の払込期間は、1年以上20年まで設定可能です。
例えば、月額5万円の掛金を10年間払い込んだ場合、掛金総額は600万円です。
この場合、解約時や死亡時には600万円の共済金が支払われます。
加入から40カ月未満での解約は掛金の額を下回って返還されてしまうので、注意が必要です。
また、契約時に受取人を指定することで、事業主が万が一のことがあった場合でも遺族が共済金を受け取れます。
事業リスクに備えつつ、税金対策としても活用できる経営セーフティ共済は、個人事業主にとっておすすめの制度です。
小規模企業共済に加入する
小規模企業共済は、個人事業主や会社の役員などが加入できる公的な共済制度です。
掛金は全額所得控除の対象となるため、所得税や住民税の節税効果があります。
また、受け取った共済金は退職所得扱いとなるため、税制上のメリットが大きいのも特長です。
小規模企業共済は月額1,000円から7万円の範囲内で自由に掛金を設定できます。
例えば、月額5万円の掛金に設定した場合、年間で60万円の所得控除が得られます。
共済金の受け取り方は一括払いと分割払いから選択でき、一括払いの場合は退職金扱い、分割払いの場合は公的年金等の雑所得として課税されるため、税負担が軽くなるのが特長です。
小規模企業共済は、個人事業主の老後の生活資金を確保するための制度ですが、税金対策としても有効です。掛金の全額所得控除や共済金の税制優遇措置により、加入者の税負担を大幅に軽減することができます。
事業リスクに備えつつ老後の生活資金を確保したい個人事業主にとって、小規模企業共済は効果的な制度です。
所得控除を受ける
個人事業主は、所得税の計算において様々な所得控除を受けることができます。
所得控除を適切に活用することで課税所得を抑え、税負担を軽減することが可能です。
個人事業主が受けられる主な所得控除は、以下の通りです。
- 基礎控除
- 扶養控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 障害者控除
- ひとり親控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 医療費控除
- 雑損控除
上記の中でも、基礎控除、扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除は比較的多くの個人事業主が利用できる控除になっています。
青色申告をする
個人事業主にとって、青色申告を行うことは税金対策で非常に重要です。
青色申告を行うためには事前に税務署に「青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要があり、承認を受けた場合は複式簿記での申告を行う必要があります。
青色申告で受けられる控除は以下の通りです。
- 最大65万円:最大控除額55万円の要件+e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存
- 最大55万円:事業所得であること、複式簿記で記帳し貸借対照表と損益計算書を添付すること、期日内申告であること
- 控除額10万円:所得税の青色申告承認申請書を提出していて青色申告が受けられること、最大65万円控除、最大55万円控除の要件を満たさない場合
青色申告を行うためには、一定の事務負担が生じます。
帳簿書類の作成や記帳には手間がかかるため、個人事業主自身での対応が難しい場合は税理士などに依頼することも検討する必要があります。
青色申告は控除額が増えるだけでなく、赤字を最大3年間繰り越せる、家族の給与を経費にできるなどのメリットもあるのでおすすめです。
30万円未満の固定資産を一括経費にする
上記の青色申告をしている個人事業主は、取得価額が30万円未満であればその全額を取得年度の必要経費として一括計上できます。
通常、事業用の固定資産を取得した場合、取得価額を耐用年数で割った金額を毎年度の減価償却費として計上します。
しかし、減価償却では経費にする期間が長くなってしまい、あまり節税効果が見込めません。
しかし、青色申告をしている個人事業主は、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産について少額減価償却資産の特例を適用できます。
例えば、パソコンを28万円で購入した場合、通常は耐用年数4年で減価償却を行い、初年度の減価償却費は7万円となります。
上記の場合、少額減価償却資産の特例措置を適用することで28万円の全額を初年度の必要経費として計上可能です。
30万円未満の少額減価償却資産を一括経費にする少額減価償却資産の特例措置は、個人事業主にとって有効な税金対策の1つです。
個人事業主は税金の種類を把握して節税対策をしていこう

個人事業主が納付する税金の種類には、住民税、所得税、消費税、個人事業税などがあります。
それぞれの税金は所得や提供するサービスなどによって計算され、決まった期日までに納付する義務があります。
少しでも税金対策をして税金を抑えたい個人事業主は、本記事で紹介した対策を試してみましょう。
また、個人事業主が月々の支払いを抑えるためには、毎月の保険料の見直しも大切です。
個人事業主が加入する国民健康保険は、家族の人数分保険料が高くなってしまいますが、社会保険に切り替えることで家族を扶養にして保険料を安く抑えることができます。
本当に保険料が安くなるか無料でシミュレーションできるので、社会保険への加入を検討したい個人事業主は以下のリンクからお気軽に保険料の見直しをしてみましょう。