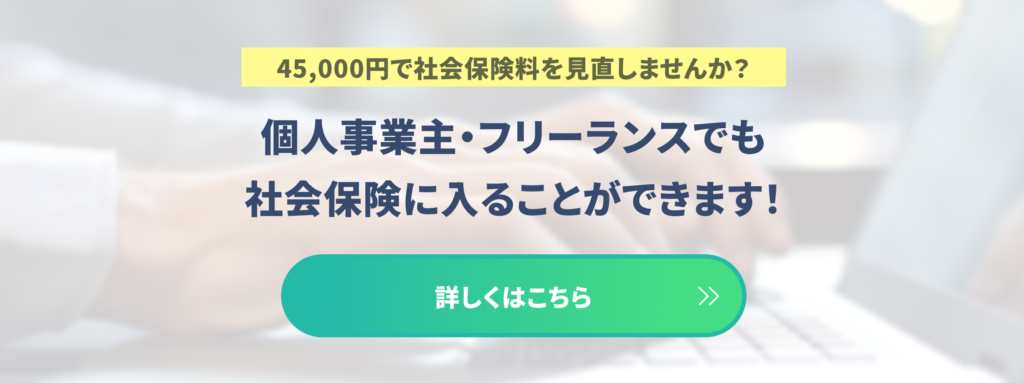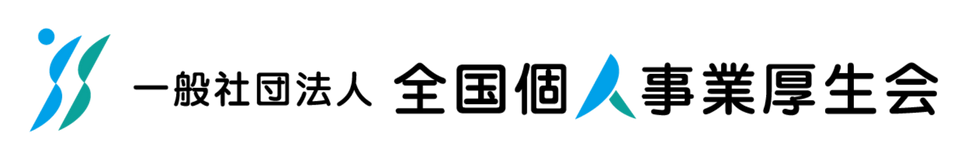会社員と違い、個人事業主には事業を営むために多くの出費が必要です。
毎月の保険料や事業の出費を差し引くと、思ったよりも収入が少ないと感じてしまう人もいるかもしれません。
本記事では、個人事業主の所得を増やすための節税の裏ワザを解説します。
保険料の節約をしたい人向けの情報も紹介するので、参考にしてみてください。
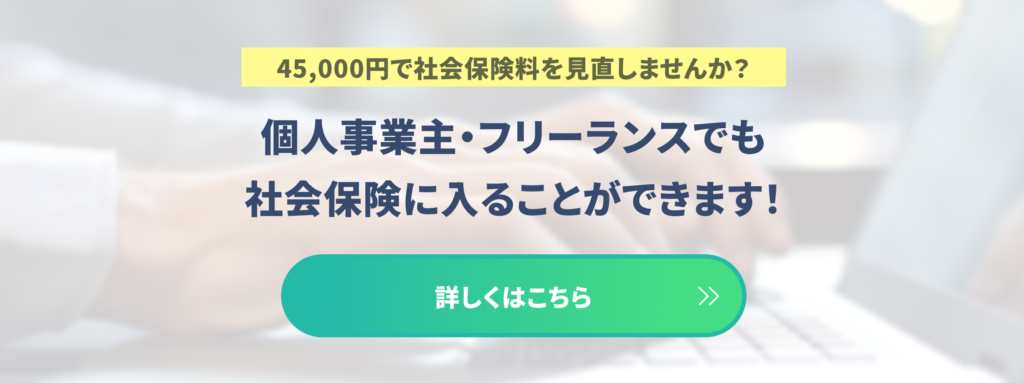
個人事業主は節税できる?

結論から言うと、個人事業主は節税が可能です。
- 個人事業主が節税で所得を増やせる理由
- 経費を上手に使って節税効果を高める
節税するためには、正しく経費を使っていく必要があります。
個人事業主が節税で所得を増やせる理由
個人事業主は、事業で発生した経費を必要経費として計上することで税負担を大幅に抑えられます。
事業収入から必要経費を差し引いた金額に対してのみ課税されるため、会社員と同じ収入でも経費を使って手取り額を増やすことが可能です。
例えば、事業に必要な書籍を購入した場合、その購入代金は全て経費として計上できます。
会社員は仕事に必要な書籍だったとしても課税された後の手取り額から支払いしなくてはいけませんが、個人事業主は課税される前に経費計上できるので、課税対象金額を減らすことが可能です。
そのため、個人事業主は会社員よりも節税しやすいのが特徴です。
経費を上手に使って節税効果を高める
経費として計上するためには、事業に必要な支出であることが大前提です。
無関係な支出まで計上するのは、脱税のリスクが伴うのでやめましょう。
事業用と私的の区分を明確にし、帳簿で正確に記録することが大切です。
事業に必要な経費は、税負担軽減のためにしっかり記帳して、経費を漏れなく計上します。
事務用品や通信費、接待交際費など、事業に関わるあらゆる支出を洗い出しましょう。
コツコツと経費計上を積み重ねることで、年間の節税効果は大きくなります。
個人事業主ができる節税の裏ワザ

個人事業主ができる節税の裏ワザを紹介します。
- 専従者給与
- 青色申告特別控除
- 少額減価償却資産の特例
- 小規模企業共済
特に、小規模企業共済は節税効果と将来への備えを同時に実現できるのでおすすめです。
専従者給与
家族を従業員として雇用して給与を支払うことで、大きな節税効果が期待できます。
配偶者や親が事業を手伝った対価として適正な範囲内で給与を支払うと、専従者給与とみなされて全額経費になります。
生活費にも回せる給与が経費になるので、有効な節税手法といえるでしょう。
ただし、働いていないのに給与を支払ったり実態に見合わない高額な支払いをしたりすると、税務調査で指摘される恐れがあります。
事業規模と家計のバランスを考え、過剰にならない給与設定を心がけましょう。
青色申告特別控除
青色申告を行うと、最大で65万円の特別控除が受けられます。
白色申告特別控除額は10万円なので、青色申告特別控除は大きな節税効果が期待できます。
会計ソフトを使えば記帳の手間も省けますし、難しい場合は税理士に確定申告書の作成を依頼するのもおすすめです。
複雑な複式簿記での記帳などの要件はありますが、青色申告特別控除の節税効果を考えると大きな節税対策になります。
記帳は面倒に感じるかもしれませんが、できるだけ早く税務署に青色申告承認申請書を提出しましょう。
少額減価償却資産の特例
30万円未満の事業用資産には、少額減価償却資産の特例を活用できます。
本来、資産の取得価額は定められた年数で減価償却するのが一般的です。
しかし、少額減価償却資産の特例を使えば、購入初年度に全額経費計上が可能になります。
パソコンやタブレット端末などの汎用品から特殊な工具や器具に至るまで、様々な少額資産が対象になります。
計画的に資産を購入すれば、初年度の所得を大幅に減らせるでしょう。
少額減価償却資産の特例は、1年間の限度額が300万円までとなっているので限度を超えないように注意が必要です。
小規模企業共済
節税と将来への備えを両立したい個人事業主におすすめしたいのが、小規模企業共済制度です。
小規模企業共済制度は掛金の全額が所得控除の対象となるため、加入するだけで毎年の税負担を大きく軽減できます。
掛金は月額1,000円から70,000円の範囲で自由に選択でき、支払った掛金は全額が所得控除の対象となります。
掛金を一括受け取りする場合は退職金扱い、分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得の扱いになるので、税負担が軽減されるのもポイントです。
また、小規模企業共済には、貸付制度もあります。
事業資金の調達や緊急時の資金需要に対応できるので、個人事業主にとって心強い味方です。
掛金の範囲内で融資を受けられるため、金利負担も比較的軽くなっています。
小規模企業共済は、事業を守るセーフティネットとしても活用できる節税の裏ワザです。
個人事業主が節税する際の注意点

個人事業主が節税する際は、以下の注意点に気をつける必要があります。
- 節税と脱税を正しく理解する
- 帳簿をつけて正確な申告を心がける
- 税理士に相談して適切な節税対策を学ぶ
特に節税と脱税の違いを理解していないと、後にトラブルになる場合があるので詳しく解説していきます。
節税と脱税を正しく理解する
適正な範囲内で税負担を抑える節税は問題ありませんが、脱税には注意が必要です。
具体的には、架空の経費を計上したり収入を過少に申告したりすると脱税とみなされます。
税務調査で脱税が発覚してしまうと、追徴課税に加えて重加算税や延滞税等のペナルティを科されます。
税金を不正に免れる脱税行為は、事業継続にも関わる重大なリスクです。
節税を行う際は、税法の枠内であることを常に意識しましょう。
税務署が疑問を持つような申告は避け、適切な節税方法を選択することが賢明です。
帳簿をつけて正確な申告を心がける
節税効果を高めるためには、日々の取引内容を帳簿に正確に記録することが重要です。
きちんと帳簿をつけていれば漏れなく経費を計上でき、節税効果も最大化できます。
いい加減な経理処理をしてしまうと、税務調査が入った際にも事実確認ができずに不利になってしまいます。
経費の区分経理を適切に行い、領収書などの必要書類は整理して保管する習慣をつけましょう。
面倒でも記帳を疎かにせず、税務署から指摘を受けるリスクを減らすことが大切です。
税理士に相談して適切な節税対策を学ぶ
節税にはコツがあり、その全てを個人事業主1人で把握するのは容易ではありません。
公的機関の情報を調べるのと合わせて、節税のプロである税理士に相談するのがおすすめです。
税理士に相談することで、事業内容に応じた具体的な節税方法を提案してもらえます。
特に、特例や控除制度の適用条件など、専門的な部分を個人事業主が全て調べるのは難しいでしょう。
自分で学ぶ姿勢を持ちつつ、税理士の力も上手に活用して着実に節税対策を身につけていくことが大切です。
個人事業主が固定費を節約する裏ワザ

個人事業主が固定費を節約する裏ワザとして、以下の方法がおすすめです。
- 事務所は自宅の一部を使うのがお得
- 光熱費は按分して経費計上する
- 設備投資は中古品の活用も検討する
固定費は節約した分だけ手取り金額が増えます。
今よりも手取り金額を増やしたい方向けに、詳細を解説していきます。
事務所は自宅の一部を使うのがお得
自宅とは別に事務所を構えると、固定費の負担が重くのしかかってしまいます。
賃料や共益費、敷金礼金など、事務所を構える際にかかる費用は安くありません。
そこで検討したいのが、自宅の一部を事務所として使うことです。
1畳分のスペースがあれば、パソコンを設置して事務所として業務をこなせます。
按分計算で、家賃の一部が必要経費になる点も大きなメリットです。
ただし、自宅と事務所の面積比で経費を按分するなど、合理的な計算が求められます。
住宅ローンを組んでいる場合は、ローンは按分できないので注意しましょう。
費用対効果を考えながら、適正に区分して家賃を経費計上していくことが重要です。
光熱費は按分して経費計上する
自宅の一部を事務所にした場合、光熱費の一部も経費とみなせます。
自宅と事務所で使用量を細かく区別するのは現実的でないので、光熱費は面積按分で計算するのが一般的です。
例えば、自宅全体の20%を事務所として使っているなら、光熱費の20%を経費計上できます。
税務署から経費性を問われた時のために、根拠となる按分資料を保管しておくことが重要です。
按分計算は面倒に感じるかもしれませんが、少しずつ積み重ねていけば節税効果は着実に上がります。
格安通信環境を構築する
インターネットや電話は個人事業主の業務に欠かせないツールですが、毎月の料金負担も小さくありません。
そこで注目したいのが、格安通信環境の構築です。
まず、携帯電話は品質にこだわり過ぎず、利用状況に合った適切な会社やプランを選ぶことが肝心です。
格安SIMを提供している各社は、通信速度では劣るものの料金が安いので固定費の節約になります。
また、固定電話にはIP電話サービスの活用がおすすめです。
IP電話は従来のアナログ回線に比べて通話料金が格段に安いので、事業を圧迫しません。
安さを追求するあまり、通信品質が著しく低下しては事業に支障をきたします。
格安通信サービスを選ぶ際は、業務内容や通信量をしっかりと把握して求められる品質を確保しましょう。
料金プランやオプションの比較検討を丁寧に行い、最適な組み合わせを見つけることが大切です。
個人事業主は節税の裏ワザを知っておくと所得を増やせる

個人事業主が所得を増やすためには、節税を積極的に行う必要があります。
節税するためには適切な経費計上、特例の活用、共済への加入などが効果的です。
少しでも節税をしたい個人事業主は、本記事で紹介した節税の裏ワザを活用してみましょう。
また、個人事業主が月々の支払いを抑えるためには、毎月の保険料の見直しも大切です。
個人事業主は原則として国民健康保険に加入しますが、社会保険に切り替えることで配偶者や家族を扶養にして保険料を安く抑えることができます。
本当に保険料が安くなるか無料でシミュレーションできるので、社会保険への加入を検討したい個人事業主は以下のリンクからお気軽に保険料の見直しをしてみましょう。