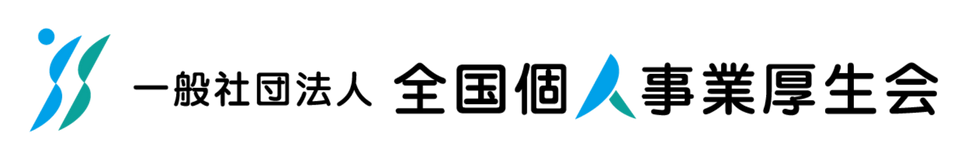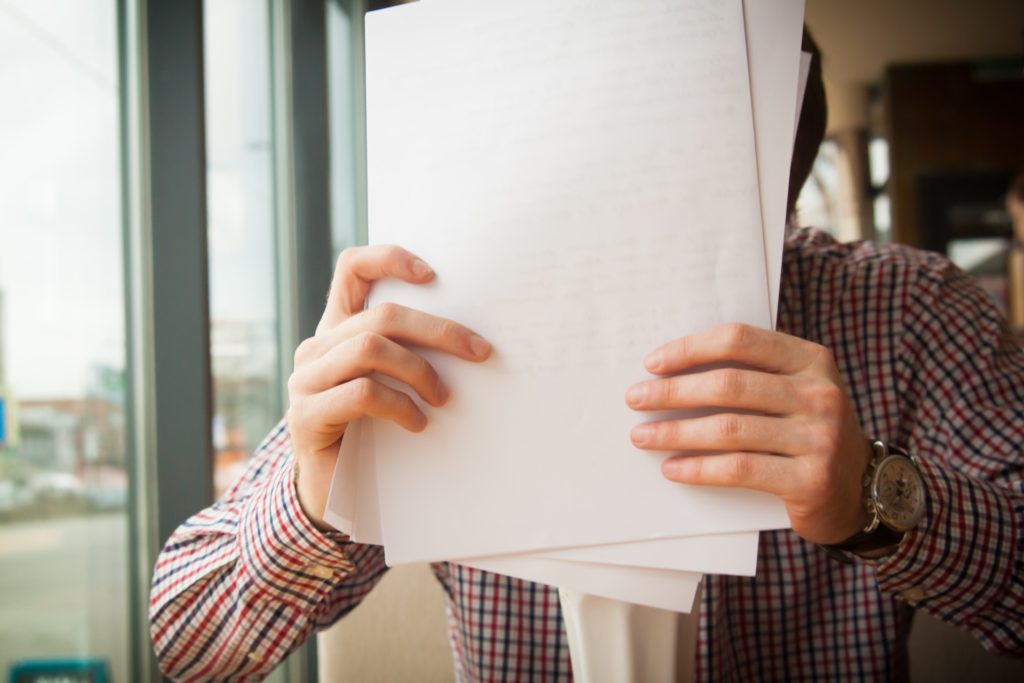個人事業主で一定条件に当てはまる場合は毎年確定申告を行う必要があります。
しかし個人事業主となって初めての確定申告はわからない内容ばかりです。
確定申告の書き方などの本もありますが、見たことない初めての単語に悩まされる人もいるでしょう。
そこで今回は、個人事業主の初めての確定申告のやり方や知っておくべき知識について解説します。
「何をみても確定申告のやり方がわからない」
「何を用意すれば良いかわからない」
「そもそも確定申告って絶対やらなきゃいけないの?」
上記のような個人事業主は必ず確認しておきましょう。
そもそも確定申告とは?
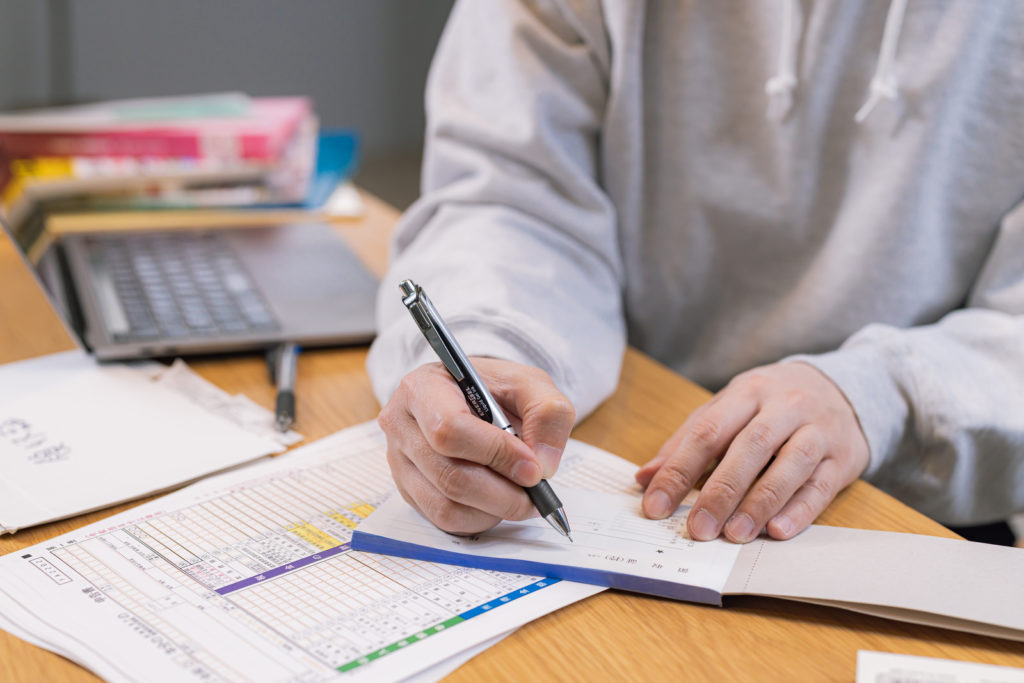
確定申告とは、年間(1月1日~12月31日)までの所得と所得税を計算して精算する手続きです。
年間の所得に対して予定納税額または源泉徴収税額が多ければ税金の還付が受けられます。
反対に納税額が少なければ不足分を納税しなければいけません。
一般的に会社員などの給与所得者は、毎月の給料から所得税が源泉徴収されており会社が年末調整を行うことで納税手続きが完了しているため、確定申告の必要はありません。
個人事業主や自営業になるとほとんどのケースで確定申告が必要になります。
確定申告で知っておきたい「所得」と「収入」
会社員から個人事業主になった方は「収入」と「所得」の違いについて知らない方もいるでしょう。
収入と所得の違いは、以下のとおりです。
- 収入…手元に入ってくる金額すべて
- 所得…収入から経費を引いた金額
たとえば個人事業主で年間の売上が500万円であれば、500万円が収入です。
しかし事業を営むなかで仕入れや交通費等で経費も発生しているはずです。経費が100万円だとすれば「全体の売上500万円-経費100万円=所得400万円」となります。
この所得となる400万円をもとに所得税が計算されます。
個人事業主で確定申告が必要ない人

個人事業主であっても所得が年間48万円以下であれば確定申告の必要はありません。
なぜなら合計所得金額が2,400万円以下の場合は、誰でも受けられる基礎控除が48万円だからです。
控除で全額を課税所得金額から差し引けるために所得税が発生しません。
反対に48万円を超える場合は確定申告をしないとペナルティが発生します。
確定申告をしなかった場合のペナルティ
確定申告の対象であるにもかかわらず申告をしなかった場合は以下のペナルティが課せられます。
| 延滞税 | ・納期限の翌日から2ヶ月以内:7.3%の加算 ・納期限の翌日から2ヶ月超:14.6%の加算 ※期間によって異なるためコチラを参照ください。 |
| 無申告加算税 | ・50万円まで:15% ・50万円を超える部分:20% |
| サービスの制限 | ・国民健康保険料・国民年金の減免、免除 ・公営住宅への入居 ・不動産物件の賃貸契約 ・ローン契約 ・クレジットカードのキャッシング ・保育料の補助 ・乳幼児医療費助成 ・児童手当 ・児童扶養手当奨学金 |
申告漏れはデメリットでしかないので、必ず期限内に確定申告をおこないましょう。
個人事業主の確定申告のやり方

初めて確定申告をおこなうときには「なにを使って申告書を作成するのか?」からわからない状態でしょう。
主な作成方法は以下の3つです。
- 手書き
- ソフトを使用
- 国税庁のWebサイト
税理士に依頼して作成してもらう方法もありますが、依頼相場が10万円ほどなので初めての確定申告では必要ないと言えます。
そのため、以下では3つの方法について解説します。
手書き
パソコンが苦手な人であれば、手書きでも確定申告書を作成できます。
申告用紙は以下の場所で入手できます。
- 国税庁のホームページ
- 税務署
- 確定申告会場
- 市町村の担当窓口
- 指導相談会場
ホームページ以外であれば用紙と合わせて確定申告書の書き方を教えてもらえます。
手書きで作成するときの細かいルールも定められているので、初めての場合は相談しながら進めていくと良いでしょう。
ソフトを使用
パソコンが得意な人であればソフトを活用しましょう。
使い慣れれば確定申告作成の時間を短縮できます。
使いやすいソフトは人によって異なるので、ここではクラウド型かインストール型の違いについて解説します。
クラウド型はネット環境さえあればいつでもアクセスできる特徴があり、月額制のサービスが多い傾向です。
インストール型は会計業務なども並行してできるのが特徴ですが初期投資は高くなります。
初めての確定申告であれば初期投資を抑えられるクラウド型が良いかもしれません。
国税庁のWebサイト
最も簡単に進められる方法が国税庁のwebサイトです。ご利用ガイドを開けば「推奨環境・利用方法・入力例・操作に関する質問」まで丁寧に解説されています。
入力例のページでは一つずつの作業を画像つきで解説してくれるので、初めての確定申告書作成でも進められるはずです。
作成後はwebからそのまま提出もできます。
初めてでもできる個人事業主の確定申告の流れ

確定申告は4つの流れで進めます。
- 必要書類の準備
- 確定申告書の記入
- 確定申告書の提出
- 所得税の納付もしくは還付
一つひとつの具体的な内容について解説します。
1.必要書類の準備
まずは確定申告に必要な5つの書類を用意しましょう。
- 確定申告書
- 所得税を確認できるもの
- 控除証明書
- 本人確認書類
- 銀行口座がわかるもの
すべての書類を提出する必要はありませんが、作成時や申告後に保管を求められる場合もありますので必ず用意しておきましょう。
それぞれの具体的な書類や入手方法についても解説します。
確定申告書
まずは確定申告書を入手してください。仕様に合った申告書でなければ申告できません。
お近くの税務署でも受け取れますし国税庁のホームページからダウンロードして印刷もできます。
所得税を確認できるもの
確定申告書を作成するには、所得金額の分かる書類が必要です。
白色申告であれば収支内訳書、青色申告であれば青色申告決算書を用意します。
それぞれの記入内容は以下のとおりです。
| 白色申告(収支内訳書) | ・1ページ目:売上・収入金額・売上原価・各種経費の内訳など ・2ページ目:売上金額や仕入金額の明細・減価償却の計算・地代家賃の内訳 |
| 青色申告(青色申告決算書) | ・1〜3ページ目:損益計算書(売上・売上原価・経費・各種引当金・準備金等・青色申告特別控除) ・4ページ目:貸借対照表・製造原価の計算 |
上記の書類も国税庁のホームページでの作成やダウンロードができます。
控除証明書
控除証明書とは、保険料などの控除対象となる支出を証明する書類です。
参考として3つの控除の例を以下の表にまとめました。
| 控除の種類 | 必要書類 |
|---|---|
| 医療費控除 | ・医療費控除の明細書 ・医療費通知 など |
| 寄附金控除 | ・寄附金の受領証 など |
| 住宅ローン控除 | ・住宅借入金等特別控除額の計算明細書 ・住民票の写し ・売買契約書の写し ・登記事項証明書の原本 ・金融機関の住宅ローンの残高証明書 |
3つのほか、所得控除には15種類ありますので以下のサイトもご確認ください。
本人確認書類
確定申告書の作成や提出には本人確認書類が必要です。マイナンバーカードが最適ですが、持っていない場合は以下の2つを用意してください。
| 番号確認書類(本人のマイナンバーを確認できる書類) | ・通知カード ・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 上記のうちいずれか一つ |
| 身元確認書類(マイナンバーの持ち主であることを確認できる書類) | ・運転免許証 ・公的医療保険の被保険者証 ・パスポート ・身体障碍者手帳 ・在留カード 上記のうちいずれか一つ |
インターネットから申告する場合はマイナンバーカードが必要となり、郵送で提出する場合は本人確認書類などを添付書類台紙に張り付けて送付します。
銀行口座がわかるもの
確定申告後の所得税の還付金は口座振込となるので、銀行口座がわかる書類を用意しましょう。
一部のネット銀行では還付金を受け取れないケースもあるので、一度確認しておきましょう。
もし銀行口座での受け取りが難しい場合は、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局に出向いて受け取る方法もあります。
2.確定申告書を記入
書類を用意したら以下の項目を「第一表・第二表」と分けて記入していきます。
- 収入金額等
- 所得金額等
- 所得から差し引かれる金額
- 税金の計算
- その他・延納の届出
- 住所・屋号・指名
- 所得の内訳
- 総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項
- 特例適用条文等
- 保険料控除等に関する事項
- 本人に関する事項
- 雑損控除に関する事項
- 寄附金控除に関する事項
- 配偶者や親族に関する事項
- 事業専従者に関する事項
- 住民税・事業税に関する事項
なお「株式等の譲渡所得・配当所得・不動産の譲渡所得・山林所得」などがある場合は、第三表。「損失申告」がある場合は、第四表も作成が必要です。
3.確定申告書を提出
確定申告書が作成できたら後は提出するだけです。
提出期限は原則として所得が発生した年の翌年2月16日から3月15日ですが、提出方法によって若干の違いがあります。
- 税務署の窓口…3月15日17時まで
- 税務署へ郵送…3月15日消印
- 電子申告でオンライン提出…3月15日24時まで
上記の期限内に提出していれば記入漏れなどの不備がある場合でもペナルティはありません(修正は発生します)。
4.所得税の納付もしくは還付
確定申告書を提出した後に還付金がある場合は約3週間で口座に振り込まれます。追加納付がある場合は確定申告書と同じ3月15日までに納税してください。
追加納付の期限が過ぎた場合は延滞税がかかるので注意しましょう。
手元のお金を残すためにもきちんと確定申告をしましょう

確定申告は納税のためでもありますが、手元にお金を残すためにも重要です。
申告をしなかったために戻ってくるはずの還付金を受け取れないケースもありますので、必ず毎年行いましょう。
また、基本的な流れを理解したら次はさらに手元のお金をどう残すかを考えていきましょう。
節税や固定費の見直しなど、個人事業主ができる工夫はいくつもあります。
なかでもぜひ見直してほしいのが社会保険料です。
基本的に個人事業主は国民健康保険や国民年金に加入しますが、個人事業主でも社会保険に加入して、月々の保険料を安くできるケースがあるのです。
以下のページで個人事業主の保険料について解説しておりますのでぜひ参考にしてください。