個人事業主として独立しようと考えている人の中には、国民健康保険への切り替えに不安を感じている人もいます。
国民健康保険は補償が少なく、万が一病気やケガをした際に生活が苦しくなってしまうためです。
結論、個人事業主でも充実した補償を受けることは可能です。
本記事では、個人事業主が加入できる保険を、職業別に解説していきます。
国民健康保険を安く抑える秘訣も紹介するので、保険料を安くしたいと考えている個人事業主は参考にしてみてください。
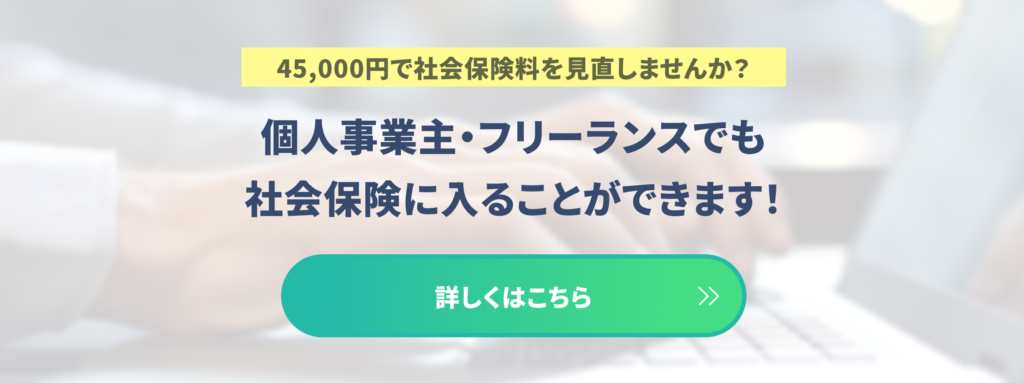
個人事業主が加入できる健康保険

個人事業主が加入できる健康保険は、以下のような種類があります。
- 国民健康保険
- 会社の健康保険の任意継続
- 各団体の国民健康保険
- 扶養として健康保険に加入
一般的な国民健康保険を中心に、それぞれの健康保険について解説していきます。
国民健康保険
会社を退職して個人事業主になると、基本的に国民健康保険への加入が必要です。
国民健康保険では、会社を退職して14日以内に市町村の役所で手続きを行います。
会社員の時は毎月の給料から天引きされていましたが、個人事業主は直接保険料を支払わなくてはいけません。
国民健康保険の計算方法は、以下の要素を基にします。
- 平等割:一世帯に定額でかかる部分
- 均等割:均等割額 × 加入者数 = 均等割
- 所得割:前年総所得金額 – 43万円 × 所得割額 = 所得割
40歳以上65歳未満は、国民健康保険料に加えて介護保険料が上乗せされます。
国民健康保険は傷病手当金がもらえない障害年金の受給は2級からになるなど、会社員の健康保険と比較して補償が少なくなってしまうのがデメリットです。
会社の健康保険の任意継続
個人事業主への転身を選んだものの少しでも補償を手厚くしたいと考える人は、会社の健康保険を任意継続するという選択肢があります。
任意継続をすることで、前職と同じ補償内容を維持することが可能です。
しかし、この任意継続には加入期間が2年という上限がある点と、会社員時代は会社と折半していた保険料を全額自己負担する点に注意が必要です。
任意継続は一時的な措置で、いずれは国民健康保険などへの切り替えが必要になると考えておきましょう。
各団体の国民健康保険
特定の業種では、独自の国民健康保険組合を持っている場合があります。
具体的には、以下のような国民健康保険組合があります。
- 文芸美術国民健康保険組合
- 東京美容国民健康保険組合
- 地方自治体ごとの国民健康保険組合
- その他
健康保険組合に加入するためには、それぞれが定める条件を満たす必要があります。
場合によっては国民健康保険よりも保険料が安くなる可能性があるため、所属する団体の公式ホームページを確認してみてください。
扶養として健康保険に加入
配偶者が会社員をしている場合、配偶者の扶養家族として健康保険に加入する方法も有効です。
扶養に入ることで個人事業主は自身で保険料を支払う必要がなくなり、配偶者の保険制度を通じて医療サービスを受けることが可能です。
扶養家族として健康保険に加入するためには、年収制限など一定の条件を満たす必要があります。
独立したばかりで収入の見込みがない個人事業主は、一時的に扶養に入って保険料を抑えることが可能です。
セラピストが個人事業主になる際に加入できる保険

セラピストとして独立を目指す際には、健康保険は必然的に国民健康保険になります。
お客様に直接触れるセラピストの場合、国民健康保険以外にも以下の保険に加入していると万が一の際に補償を受けられます。
- 生産物賠償責任保険
- 受託者賠償責任保険
- 事業活動総合保険
生産物賠償責任保険は、サロンで販売した商品でお客様の肌や体に傷を付けてしまった際の損害賠償を保証してくれる保険です。
受託者賠償責任保険は、施術中に預かったお客様の服や荷物を汚したり紛失したりした際の損害賠償を保証してくれます。
事業活動総合保険は、自然災害などに被災して業務ができなくなった際の休業期間を補償してくれる保険です。
国民健康保険だけでは不安があるセラピストは、上記の保険も検討してみてください。
個人事業主として営業を始める際に加入できる保険

個人事業主として営業職を始める人は、会社の健康保険から国民健康保険への切り替えが必要です。
外回りの営業中に交通事故に遭遇した場合や営業目標達成のための過重労働が原因で体調を崩した場合に、国民健康保険だけではカバーしきれない医療費や休業補償を受けるためには、個別の保険に加入するしかありません。
個人事業主やフリーランスが加入できる保険として、フリーランス賠償責任補償があります。
フリーランス賠償責任補償は、フリーランスやパラレルワーカーを支援するために設立された一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会が提供している保険です。
業務中の対人や対物事故、情報漏洩など営業職に関わるトラブルを補償してくれるため、外回りの多い営業職をサポートしてくれます。
個人事業主として建設業や土木業を始める際に加入できる保険

個人事業主として建設業や土木業などの力仕事に従事する人は、一般的な会社員よりも事故やケガのリスクが大きくなります。
そんな危険を伴う仕事に従事する個人事業主の加入できる保険について、それぞれ解説していきます。
個人事業主で建設業を始める場合
建設業を営む個人事業主は、専門的なスキルと同じくらいリスク管理も要求されます。
この業界で事業を始める際には、事故や怪我のリスクが高いため、適切な健康保険への加入が不可欠です。
基本的には国民健康保険に加入し、特別加入を活用して労災保険への加入も検討しましょう。
一人親方の労災保険加入については、以下の記事で詳しく解説しています。
労災保険に加入すると、建設業特有の機械操作や高所作業などでケガをした際の保証が手厚くなります。
個人事業主で土木業を始める場合
土木業を営む個人事業主も建設業と同様に、大型機械の使用に伴う事故やケガのリスクが高くなります。
そのため、国民健康保険と労災保険への加入が必要です。
個人事業主は労災保険に加入できないと考えている人もいますが、土木や建築などの一人親方は特別加入という制度を活用して労災保険に加入できます。
労災保険に加入すると万が一の補償を受けられるだけでなく、発注者からの信頼獲得にもつながります。
ケガで長期的に仕事ができなくなっても補償を受けられるので、通院や生活費の補填が可能です。
個人事業主で電気工事を始める場合
電気工事業を営む個人事業主は、作業の特性上、感電事故や火災などのリスクが伴います。
そのため、基本となる国民健康保険に加えて労災保険への加入が必要です。
電気工事も一人親方として事業展開する際は特別加入で労災保険に加入できます。
また、以下のような保険への加入も検討してみましょう。
- 請負業者賠償責任保険
- 生産物賠償責任保険(PL保険)
請負業者賠償責任保険は、仕事中に他人へ損害を与えてしまった場合の賠償金を補償する保険です。
周辺の人がケガをしてしまった場合や、現場で依頼主の備品を壊してしまった際も補償対象になります。
PL保険は、施工不良で住宅に損害を与えてしまった場合の補償をしてくれます。
施工完了後のトラブルを補償してくれるため、長く電気工事を続けていくためには欠かせない保険です。
美容系の個人事業主が加入できる保険

美容系の個人事業主が加入できる保険を紹介していきます。
今回紹介するのは、以下の職種です。
- 美容師
- ネイリスト
それぞれの職種を基に、美容系個人事業主の保険の仕組みについて解説していきます。
美容師が加入できる保険
美容師として独立する場合、加入できる健康保険は以下の2種類です。
- 国民健康保険
- 美容健康保険組合
国民健康保険は特別な加入条件はありませんが、美容健康保険組合の健康保険に加入するためには一定の条件があります。
美容健康保険組合は大きく分けて、全日本理美容健康保険組合、東京美容国民健康保険組合、大阪府整容国民健康保険組合の3種類が存在します。
全日本理美容健康保険組合は、東京都内にサロンを構えている美容師が対象です。
東京美容国民健康保険組合は、東京都や周辺の県に在籍していることが基本的な条件です。
大阪府整容国民健康保険組合は、大阪府か奈良県に住民票を置いてる美容師が対象になります。
店舗を持たないフリーランス美容師は大阪府整容国民健康保険組合に加入できないので、注意しましょう。
ネイリストが加入できる保険
ネイリストが加入できる健康保険は、以下のとおりです。
- 国民健康保険
- 美容健康保険組合
美容健康保険組合は、美容師に限った組合ではありません。
ネイリストを含め、美容に関わる事業を営む個人事業主が加入対象です。
また、セラピスト同様にサロンを経営する際は、以下の保険に加入しておくとお客様のケガや荷物の破損時に補償を受けられます。
- 生産物賠償責任保険
- 受託者賠償責任保険
- 事業活動総合保険
美容系の個人事業主は、建設業や土木業のように労災保険には加入できません。
国民健康保険だけでは不安があると考える人は、自分で保険を選んでみましょう。
個人事業主として清掃業を開業する際に加入できる保険

個人事業主として清掃業を始める人が加入できる保険についても解説していきます。
今回は、以下の職種を基にしました。
- ハウスクリーニング
- その他の清掃業
清掃業を開業予定の人は、参考にしてみてください。
個人事業主としてハウスクリーニングを始める場合
個人事業主としてハウスクリーニングを始める場合、健康保険は国民健康保険になります。
清掃業界には組合がないので、国民健康保険以外の選択肢はありません。
配偶者や子どもがいる場合は全員分の国民健康保険を支払わないといけないため、保険料が高額になってしまうでしょう。
また、ハウスクリーニングも以下のような賠償責任保険への加入をおすすめします。
- 請負業者賠償責任保険
- 生産物賠償責任保険(PL保険)
ハウスクリーニングはお客様の家の中で作業をするため、家財や電化製品を破損する可能性があるためです。
その他の清掃業を始める場合
以下のような清掃業は、国民健康保険だけでなく一人親方として労災保険への特別加入が認められます。
- 美装工事
- 家洗工事
美装工事は、建設現場でのクリーニング工事のことです。
店舗や施設の新築現場では、工事が終わった後に汚れを取り除く美装工事が必要です。
建設業の許可の業種としては、清掃施設工事業や内装仕上工事業に該当します。
家洗工事は、建物の木部の汚れを落とす職種です。
内装工事が終わった後に、専用の薬品などを使って木材の艶出しを行います。
上記のような職種は清掃業というよりも建設業に近いため、一人親方として認められます。
まとめ

個人事業主が加入できる健康保険は、基本的に国民健康保険になります。
国民健康保険は補償が少ない上に家族が増えると保険料も増えるため、大きな負担になる場合があります。
個人事業主が社会保険に加入出来たら、配偶者や子どもを扶養に入れて保険料を節約できるでしょう。
一般社団法人全国個人事業厚生会では、個人事業主やフリーランスでも加入できる社会保険を提供しています。
社労士への労務相談ができるだけでなく、面倒な手続きも全て代行してくれます。
少しでも健康保険料を節約したい、もっと手厚い補償を受けたいと考えている個人事業主やフリーランスは、以下のリンクからシミュレーションをしてみましょう。
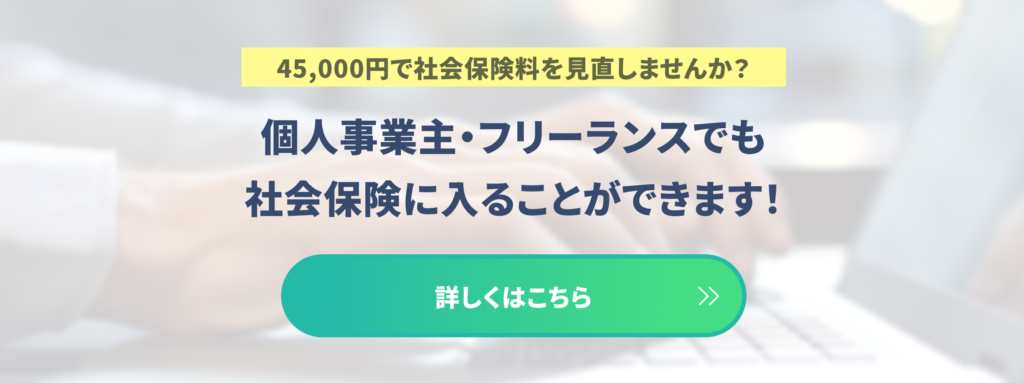
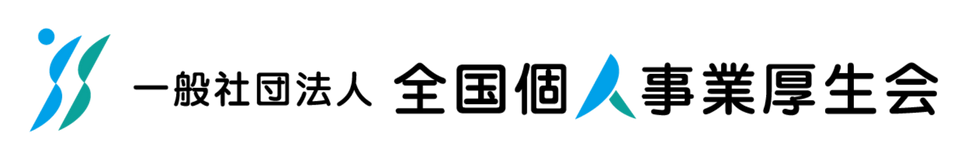
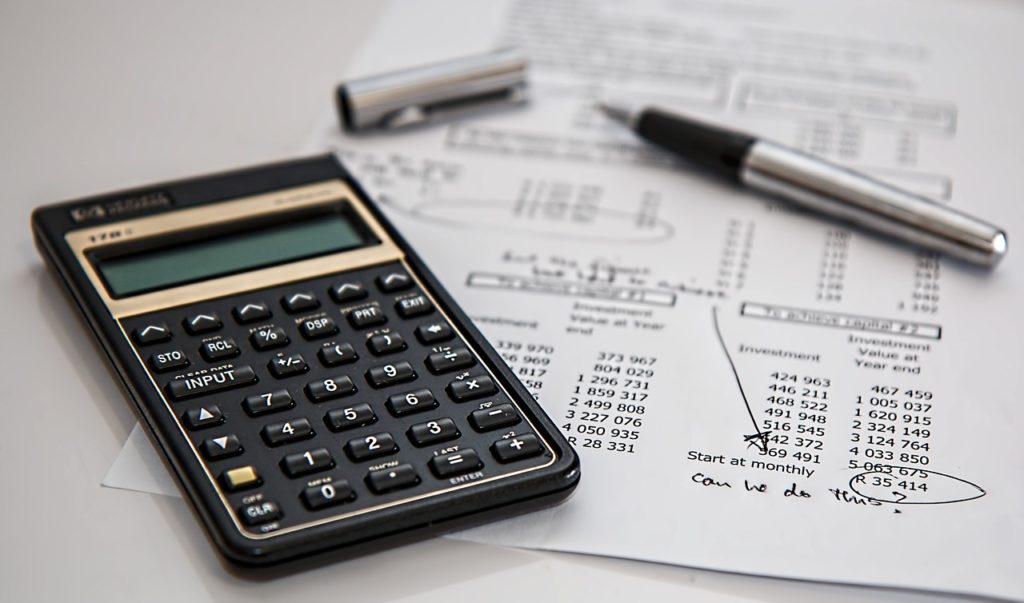

 nwa.or.jp
nwa.or.jp