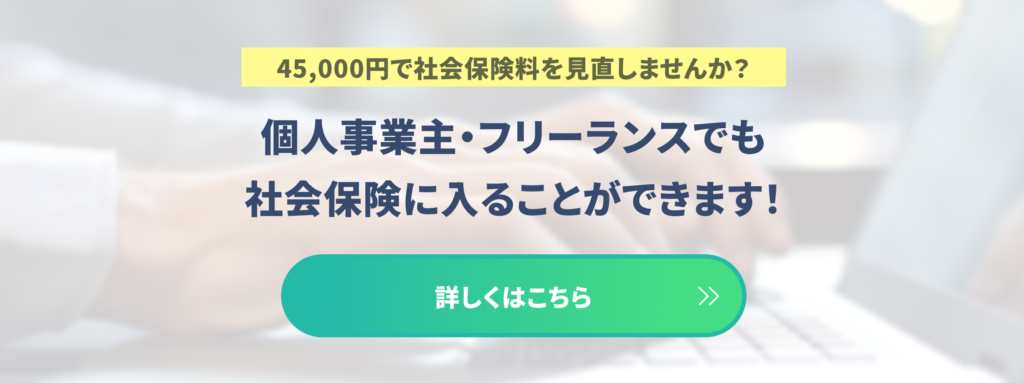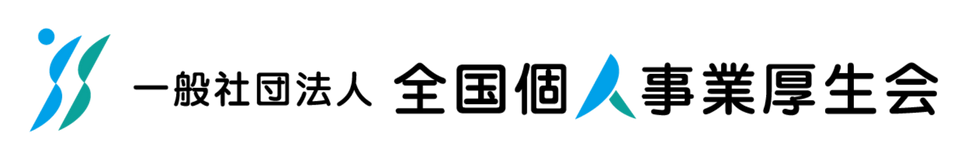労働者と同じように現場仕事に従事する一人親方の中には、労災保険に加入していない人もいます。
「一人親方は労災保険に加入できないのでは?」
と考えている人もいるかもしれませんが、結論として一人親方も労災保険に加入できます。
というか、むしろ入らないとデメリットになってしまうことがあります。
本記事では、一人親方が加入できる労災保険の条件、メリット、適用範囲と、一人親方と個人事業主の違いについて解説していきます。
負担の大きい国民健康保険を抑えるコツも紹介するので、保険料を安くしたいと考えている一人親方は参考にしてみてください。
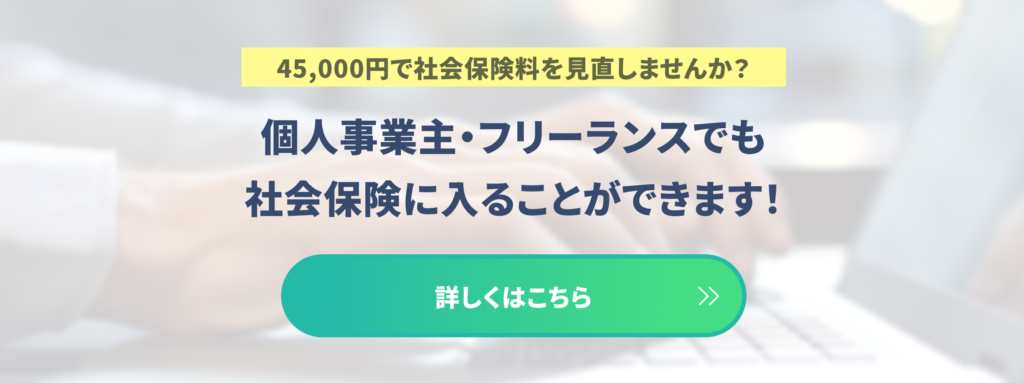
一人親方の労災保険とは?

一人親方の労災保険とは、事業を営む一人親方が業務中に発生した事故や怪我による損害を補償するための保険制度です。
危険を伴う業種で活動する一人親方は、従業員を雇用しないことから一般の労災保険制度の適用外となります。
以下で、一人親方と労災保険の基本を解説していきます。
一人親方とは?
一人親方は、他の従業員を雇用せずに自らが直接作業を行う個人事業主です。
万が一の事故や怪我が発生した場合に備え、労災保険へ加入したいのが本音でしょう。
しかし、一人親方は通常の労災保険には加入できないケースがあり、不安を抱える人が多いのが現状です。
一人親方の労災保険が重要な理由
一人親方は、建設現場での転落や林業での樹木伐採中の事故など、予期せぬ状況で負傷するリスクがあります。
そのリスクに対しても、労災保険は治療費や休業中の補償を行ってくれます。
労災保険によって一人親方は金銭的な負担が軽減され、安定して事業を維持できるでしょう。
労災保険への加入は、一人親方だけでなく、取引先やクライアントに対して事業の信頼性を高める制度です。
一人親方労災保険の特別加入制度と金額

一人親方が労災保険に加入するためには、特別加入が必須です。
以下では「特別加入の仕組み、加入条件、料金の事例」について解説していきます。
特別加入制度とは?
特別加入制度は、一般的な労災保険に加入できない一人親方を対象とした、任意加入制度です。
労働者と同じく、労働の実態と災害の発生状況を判断して保護が必要だとみなされると加入できます。
特別加入団体に加入することで、労災保険の補償を受けられるようになります。
また、特別加入団体を通じて提供される保険プランは一人親方の業務内容やリスクの度合いに応じて異なるため、最適な補償内容を選択することが重要です。
特別加入の条件
特別加入を利用するためには、一人親方が以下の条件を満たしている必要があります。
- 一人で事業に従事する個人事業主又は法人の代表者
- 年間延べ100日未満しか労働者を使用しない個人事業主又は法人の代表者
一人親方でも、グループで仕事をしているケースや同一の屋号を使用している場合は、特別加入が認められないことがあります。
グループで仕事を受注すると、労働者供給事業とみなされる可能性があるためです。
特別加入の条件をクリアすることで、一人親方は労災保険の特別加入資格を得られ、業務中の事故や怪我から身を守れます。
一人親方と個人事業主は違う?

一人親方と個人事業主は混同されがちですが、実際には異なる事業形態です。
具体的には、業務の性質、従業員の雇用状況、そして労災保険への加入資格などで違いがあります。
以下、一人親方と個人事業主の違いについて解説していきます。
一人親方と個人事業主の定義
一人親方は、以下のような業種の個人事業主です。
- 建設業
- 林業
一方の個人事業主は、以下のような業種で用いられます。
- ITエンジニア
- Youtuber
- クリエイター
- スポーツ選手
- 運送業
- 個人レストラン
業種によって、一人親方と個人事業主の定義は変わってきます。
従業員の雇用の有無
一人親方は従業員を雇用しない働き方が特徴です。
全ての業務を自分で行うため、労災保険の特別加入が可能となる条件を満たしやすいのがメリットです。
個人事業主は、事業の規模や業務の性質に応じて従業員を雇用することがあります。
従業員を雇用する場合、事業主は従業員分の労災保険加入が義務付けられるため、労災保険の管理がより複雑になります。
労災保険への加入資格
個人事業主は労災保険だけでなく、雇用保険や社会保険にも加入できません。
従業員を雇用した場合は、従業員を対象に労災保険と場合によって雇用保険の加入義務が生じます。
従業員が5人以上いる場合は社会保険も必須です。
一人親方は従業員を雇用しないことなどの条件を満たすことで、労災保険に特別加入できます。
従業員を雇用しても、年間100日以内に限って特別加入の対象になります。
一人親方が労災保険に特別加入するメリット

労災保険への特別加入は、一人親方にとってメリットがあります。
以下、一人親方が労災保険に特別加入するメリットを解説していきます。
仕事の依頼が増える
一人親方が労災保険に加入しているという事実は、事業主やクライアントにとって安心材料です。
特に建設業や林業などの高リスクが伴う業種においては、労災保険への加入は事業の信頼性を大きく高めます。
そのため、建設プロジェクトの発注者は、契約する一人親方が労災保険に加入していることを求めるケースが多くなります。
労災保険に加入している一人親方は、仕事を受注する機会が増える点がメリットです。
労災保険への加入は、仕事の依頼を増やす効果的なアピール手段となります。
補償を受けられる
労災保険への特別加入は、万が一働けなくなった際に補償を受けられます。
事故や怪我が発生した際の治療費、業務不能となった場合の休業補償、さらには重度の障害が残った場合の障害給付など、幅広い補償を受けることが可能です。
例えば、工事現場で誤って転落してしまった場合や機械操作中の怪我など、予期せぬ事故が発生した場合でも補償の対象になります。
事故や怪我の補償は、一人親方が安心して事業を継続するために大切な要素になります。
一人親方の労災保険の補償対象

建設業や林業などの一人親方にとって労災保険は、業務実施中に発生する様々なリスクに対する重要な補償制度です。
以下、建設業と林業における労災保険の補償対象について、具体的な例を交えながら解説していきます。
建設業の業務災害時の補償範囲
建設業に従事する一人親方が業務災害に直面した際、補償範囲は以下の通りです。
- 請負契約に直接必要な業務
- 請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
- 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
- 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)およびこれに直接附帯する行為を行う場合
- 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合
建設業の一人親方は、上記のように業務に関わる多くの場面が補償範囲となります。
林業の業務災害時の補償範囲
林業に従事する一人親方が業務災害に直面した際、補償範囲は以下の通りです。
- 森林の中の作業地、木材の搬出のための作業路およびこれに前後する土場における作業並びにこれに直接附帯する行為を行う場合
- 作業のための準備・後始末、機械等の保管、作業の打ち合わせなどを通常行っている場所(自宅を除く場所で、以下「集合解散場所」という)における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
- 集合解散場所と森林の中の作業地の間の移動およびこれに直接附帯する行為を行う場合
- 作業に使用する大型の機械等を運搬する作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
- 台風、火災などの突発事故による緊急用務のために作業地または集合解散場所に赴く場合
引用:厚生労働省「労災保険 特別加入のしおり」P.10~P.11
林業に従事する一人親方も、伐採作業や機械操作中に多大なリスクにさらされます。
木の伐採中に誤って転倒する、機械操作中に事故が発生するなど、林業特有の危険が存在します。
労災保険への特別加入をしている一人親方は、上記の業務が補償範囲になるため、仕事に注力できるでしょう。
一人親方は労災保険に入ってさえいればいいのか
ここまで一人親方の労災保険についてご紹介しましたが、労災保険だけに入っていればいいのでしょうか?
答えはNoです。一人親方は通常だと国民健康保険と国民年金へ加入し、保険料を支払う必要があります。
ご存じの方も多いかも知れませんが、国民健康保険は会社員が加入している社会保険に比べて保険料が高くなるケースがあり、一人親方の保険料の負担は会社員より多くなってしまいます。
一人親方が保険料の負担を減らすコツ
一人親方が国民健康保険料の負担を減らすためには、社会保険への加入がおすすめです。
国民健康保険は配偶者や子どもの人数分だけ保険料が発生しますが、社会保険は世帯主の扶養に入ることで配偶者や子どもの保険料が免除されるためです。
さらに、社会保険には傷病手当もあるため、万が一の事故や怪我の際にも補償が増える点がメリットです。
通常だと一人親方や個人事業主の方は社会保険に加入できませんが、全国個人事業厚生会に加入いただくと一人親方でも社会保険に入ることができます。一人親方の社会保険加入については、以下で詳細に解説しています。
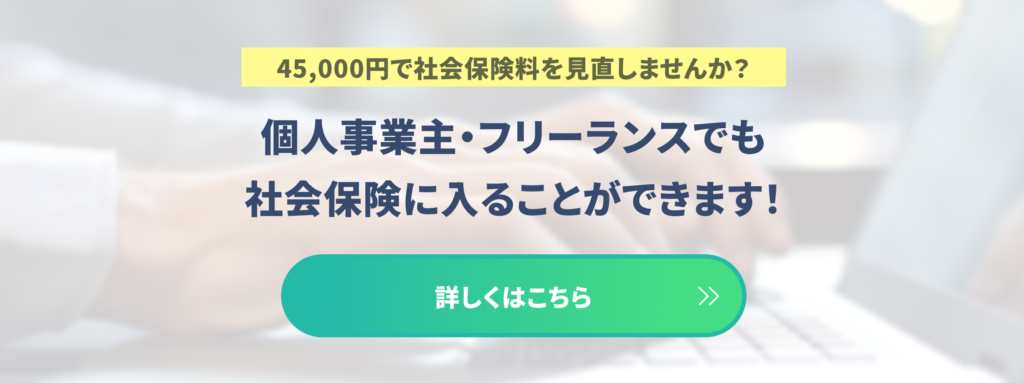
まとめ

一人親方でも、特別加入制度を使って労災保険に加入できます。
事業主やクライアントは安定を求めているため、労災保険に加入していると仕事を受注しやすくなるというメリットもあります。
仕事中の事故や怪我も補償されるので、より一層事業と生活も安定するでしょう。
労災保険と国民健康保険の支払いは負担になる可能性がありますが、社会保険に加入すると配偶者や子どもを扶養できるため、月々の保険料を節約できます。
どの程度保険料をお得にできるかは、以下のページで詳しく解説しています。