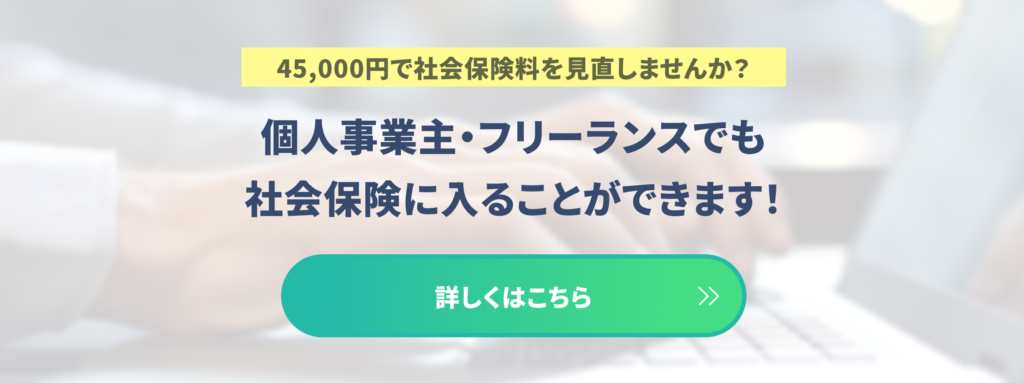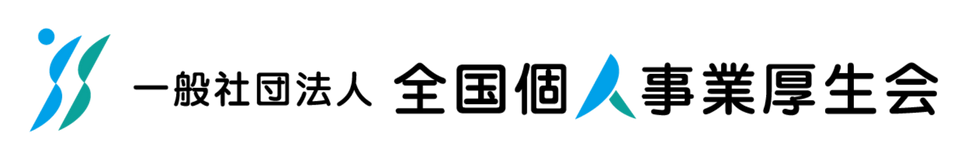「事業を拡大したい、新しい設備を導入したい」
そう考えた時に、資金が足りずに悩んでいる個人事業主もいるでしょう。
そんな個人事業主には、補助金の活用がおすすめです。
本記事では、個人事業主向けの補助金一覧から補助金の審査に通過するコツ、固定費の見直しまで解説していきます。
固定費となる社会保険料の見直しも紹介しているので、資金繰りで悩んでいる個人事業主は参考にしてみてください。
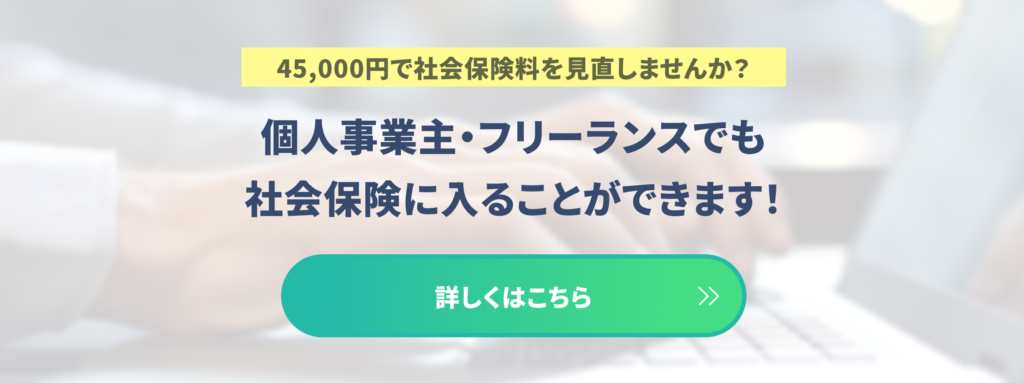
2024年度の個人事業主向けの補助金一覧

まずは、2024年度の個人事業主向けの補助金をまとめました。
- 小規模事業者持続化補助金
- 事業再構築補助金
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
- IT導入補助金
- 事業承継・引継ぎ補助金
特に、最大で200万円の補助金を受け取れる小規模事業者持続化補助金の申請をおすすめします。
小規模事業者持続化補助金
個人事業主を含む小規模事業者は、業種やビジネス内容を問わずに小規模事業者持続化補助金が利用できます。
対象者は、以下の条件に該当する事業主です。
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数20人以下 |
| 製造業その他 | 常時使用する従業員の数20人以下 |
小規模事業者持続化補助金となる経費は、以下の通りです。
- 機械装置等費:補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
- 広報費:新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
- ウェブサイト関連費:ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費
- 展示会等出展費:展示会・商談会の出展料等
- 旅費:販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
- 開発費:新商品の試作品開発等に伴う経費
- 資料購入費:補助事業に関連する資料・図書等
- 雑役務費:補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
- 借料:機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
- 設備処分費:新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
- 委託・外注費:店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)
売上げ向上を目指す個人事業主にとって、小規模事業者持続化補助金はさまざまな用途に使えるため便利です。
具体的には、新商品開発や新サービスの立ち上げ、マーケティング強化、設備投資などに活用できるので、事業の成長に大きく貢献するでしょう。
通常枠の上限は50万円ですが、賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠では最大200万円まで補助になります。
参照:全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック」
事業再構築補助金
新型コロナウイルスの影響により、売上げが大きく落ち込んでしまった個人事業主を救済するために、事業再構築補助金は設立されました。
この事業再構築補助金は、新分野展開や事業転換、事業再編などに意欲的に取り組む個人事業主や小規模事業者が対象です。
以下、業種別の対象範囲をまとめました。
| 製造業その他 | 資本金3億円以下の会社又は従業員数300人以下の会社及び個人 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人 |
| 小売業 | 資本金5千万円以下の会社又は従業員数50人以下の会社及び個人 |
| サービス業 | 資本金5千万円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人 |
補助の対象となる経費は、以下の通りです。
- 建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復、貸し工場・貸店舗等の一時移転)
- 機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費、運搬費
- 技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
- 外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費 ※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。
- 広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
- 研修費(教育訓練費、講座受講等)
事業再構築補助金を申請する際は、売上減少を証明する書類の他に以下の書類が必要です。
- 事業計画書
- 財務資料やその他、補助金申請に関わる様式類
それぞれの補助金の枠は以下の図のようになっています。

新しいビジネスモデルの構築を目指す個人事業主にとって、この補助金は大きな後押しとなるでしょう。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、令和5年度は2,000億円の予算を投じた補助金です。
個人事業主や中小企業を対象に、サービス開発や生産性向上に向けた支援策として2024年度も継続して実施されます。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の対象者は、以下の通りです。
- 個人事業主や中小企業
- 革新的な製品・サービスの開発、生産プロセス等の省力化に必要な設備投資を予定している
例えば、生産ラインの自動化や無人化、クラウドサービスの導入などに同補助金を投じることで、大幅な生産性向上を実現可能です。
その他の概要は、下の図のようになっています。

引用:中小企業庁技術・経営革新課「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金について(Ver.1.1)」
IT導入補助金
デジタル化の波が加速する中、ITツールの活用は個人事業主にとっても避けて通れない課題となっています。
政府は個人事業主や小規模事業者のIT化を後押しするため、IT導入補助金制度を設けています。
IT導入補助金を申請する際は、以下の書類が必要です。
- 事業計画書(IT導入による事業効率化や競争力向上の計画を記述する文書)
- 事業の健全性や投資の妥当性を示すための財務資料
以下、補助枠については、以下の枠が用意されています。
- 通常枠
- インボイス枠(インボイス対応類型)
- インボイス枠(電子取引類型)
- セキュリティ対策推進枠
通常枠
通常枠は、自社に合ったITツールを導入することで業務効率化と売上アップをサポートします。
補助率は一律で1/2以内となっており、補助額は以下の通りです。
- 1プロセス以上の補助額:5万円以上150万円未満
- 4プロセス以上の補助額:150万円以上450万円以下
対象となるITツールの例を紹介します。
- 供給・在庫・物流
- 総務・人事・給与・労務
- 顧客対応販売支援
この補助金を利用すれば、基幹システムの入替えや専用ソフトの導入、クラウドサービスの活用など、さまざまなIT投資が可能になります。
インボイス枠(インボイス対応類型)
インボイス対応類型のインボイス枠は、インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトの導入によって業務をサポートします。
ソフト面の補助率と補助額は、以下の通りです。
| 補助率 | 補助額 |
| 3/4以内(中小企業)、4/5以内(小規模事業者) | 50万円以下 |
| 2/3以内 | 50万円超〜350万円以下 |
パソコンやハードウェア類の補助についてもまとめました。
| 補助対象 | 補助率 | 補助額 |
| パソコン・タブレット等 | 1/2以内 | 10万円以下 |
| レジ・券売機等 | 1/2以内 | 20万円以下 |
対象となるITツールの例を紹介します。
- 会計ソフト
- 受発注ソフト
- 決済ソフト
- パソコン・ハードウェア
インボイス対応類型のインボイス枠を活用することで、インボイス制度に必要なハードウェアやソフトを導入できます。
インボイス枠(電子取引類型)
電子取引型のインボイス枠は、インボイス制度に対応した受発注システムを商流単位で導入する企業を支援します。
以下、補助率と補助額をまとめました。
| 補助率 | 補助額 | |
| 中小企業 小規模事業者等 | 2/3以内 | (下限なし)~350万円以下 |
| その他事業者等 | 1/2以内 | (下限なし)~350万円以下 |
対象となるITツールは受発注システムです。
条件を満たせば、受発注システムの導入費用を一部負担してもらえます。
セキュリティ対策推進枠
セキュリティ対策推進枠は、サイバー攻撃から事業を守るための補助金です。
補助率は一律で1/2以内となっており、補助額は5万円以上100万円以下です。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているサービスをメインのITツールとした申請(「サイバーセキュリティお助け隊サービス」単品での申請)に、導入費用と最大で2年分のサービス利用料を補助してもらえます。
事業承継・引継ぎ補助金
個人事業主の高齢化が進む中、事業の円滑な承継や引き継ぎが課題となっています。
事業承継・引継ぎ補助金は、既存の事業もしくは廃業した事業を継承または引き継ぎする際に活用できる補助金です。
この補助金は、M&A、事業承継、事業引継ぎ、経営資源や株式譲渡に係る費用の一部を支援するものです。
補助額は種類によって100万円~800万円までとなっています。
具体的な手続きの流れは以下の通りです。
- 認定⽀援機関や専⾨家などへの相談
- 「jGrants」にて交付申請
- 事業状況の報告
- 実績報告
- 補助金交付請求
- 事業化の状況報告
自社株の評価費用や後継者教育費用など、事業承継に伴う初期費用を賄うのに有効活用できるでしょう。
補助金・助成金・給付金の違い

個人事業主は、補助金の他に助成金や給付金をもらうこともできます。
それぞれの違いについて、以下で解説していきます。
補助金は審査に通過する必要がある
補助金は個人事業主や中小企業が、新しい取り組みや事業展開を行う際に受給できる公的な支援策の1つです。
ただし、補助金を申請する際には審査があり、事業計画の内容など、一定の基準を満たす必要があります。
特に個人事業主の場合は、事業の詳細な計画や補助金のシミュレーションを提示することが大切です。
申請書類の作成には手間も時間もかかりますが、通過すれば資金面で事業を後押ししてくれる制度です。
助成金は条件を満たせば受給可能
助成金は、一定の基準や条件を満たしていれば審査は厳しくありません。
企業や事業者側にインセンティブがなくても良いため、手続きが簡素化されているのも助成金のメリットです。
緊急的な資金繰り対策など、目的が限定されていることが多いのが助成金の特徴です。
給付金は緊急時の救済措置
給付金は、災害などの緊急事態発生時に個人事業主の生活や事業継続を下支えするためのセーフティネットとして提供されます。
給付金は臨時的かつ一時的な性質が強いため、事業の継続的な発展を後押しするものではありません。
災害などで生活や事業が危機的な状況を回避するのが目的としています。
個人事業主が補助金の審査を通過するためのコツ

個人事業主が補助金の審査を通過するためには、以下のコツがあります。
- 締切りに間に合うように準備を進める
- 目的や条件を明確にしておく
特に補助金は用途が限定されているため、明確な目的を設定しておくことが大切です。
締切りに間に合うように準備を進める
補助金の審査を通過するためには、締切りに間に合うように事前の準備を怠らないことが大切です。
多くの補助金制度には受付期間や予算の上限が設定されており、日時や予算を超えてしまうと書類を整えても受理されません。
実際、補助金の申請書類を揃えるだけでも、かなりの労力を要するでしょう。
特に個人事業主の場合、本業と並行して準備をすすめる必要があるため、時間的な制約が大きくなります。
そこで、余裕を持って以下の準備を進める必要があります。
- 補助金の申請要領や必要書類のリストアップ
- 補助対象事業の検討や計画の具体化
- 書類の作成と見直し
準備が整った時点で申請を行えば、通過のチャンスが高まるでしょう。
目的や条件を明確にしておく
補助金の審査を通過するためには、補助事業の目的や実施内容、事業の条件などを明確にしておく必要があります。
個人事業主の場合は、事業計画と補助金の条件をしっかりと照らし合わせなければなりません。
例えば、経費の節減や生産性向上、新規販路開拓など、事業目的や課題をあらかじめ明確化しておきましょう。
また、事業の特徴や成長可能性といった点についてもアピールできるよう準備しておきます。
目的意識を持って準備を進めれば、審査員に対してもわかりやすく訴求できます。
事業資金を効率よく使うためには保険料の見直しが大切
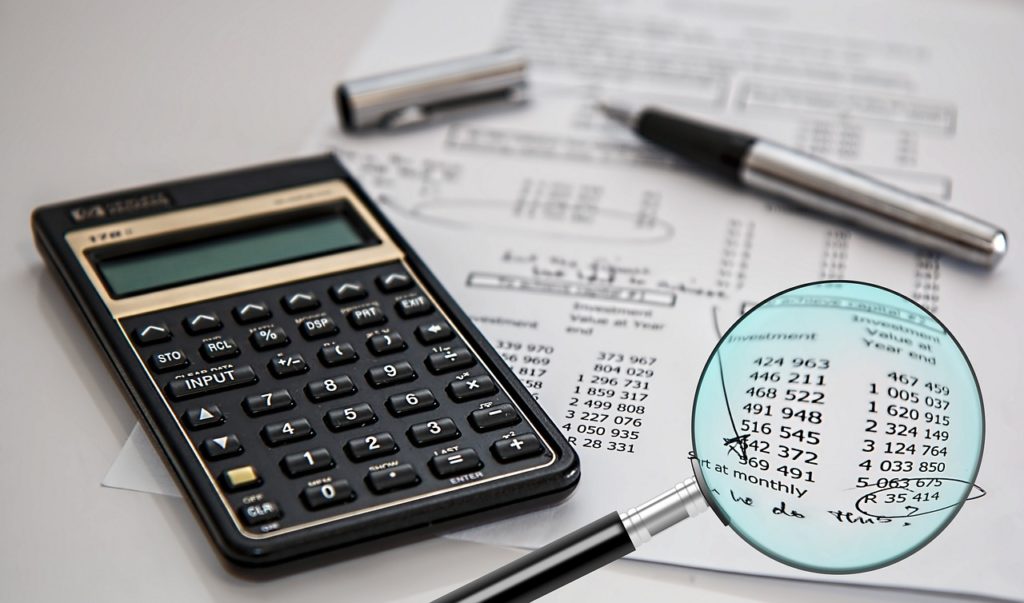
補助金は事業資金を効率よく使うために効果的ですが、日頃から保険料の見直しなどもしておくことが大切です。
保険料は固定費となって毎月発生するので、月々の支払いを抑えると年間での利益が大きくなるでしょう。
国民健康保険料は自分1人だけでなく、扶養する家族の人数分だけ高額になってしまいます。
個人事業主が保険料を少しでも安く抑えて会社員と同様の補償を受けるためには、一般社団法人全国個人事業厚生会の社会保険への加入がおすすめです。
いつでも無料で相談できて専門家が丁寧にシミュレーションしてくれるので、扶養家族がいる個人事業主は気軽に相談してみてください。